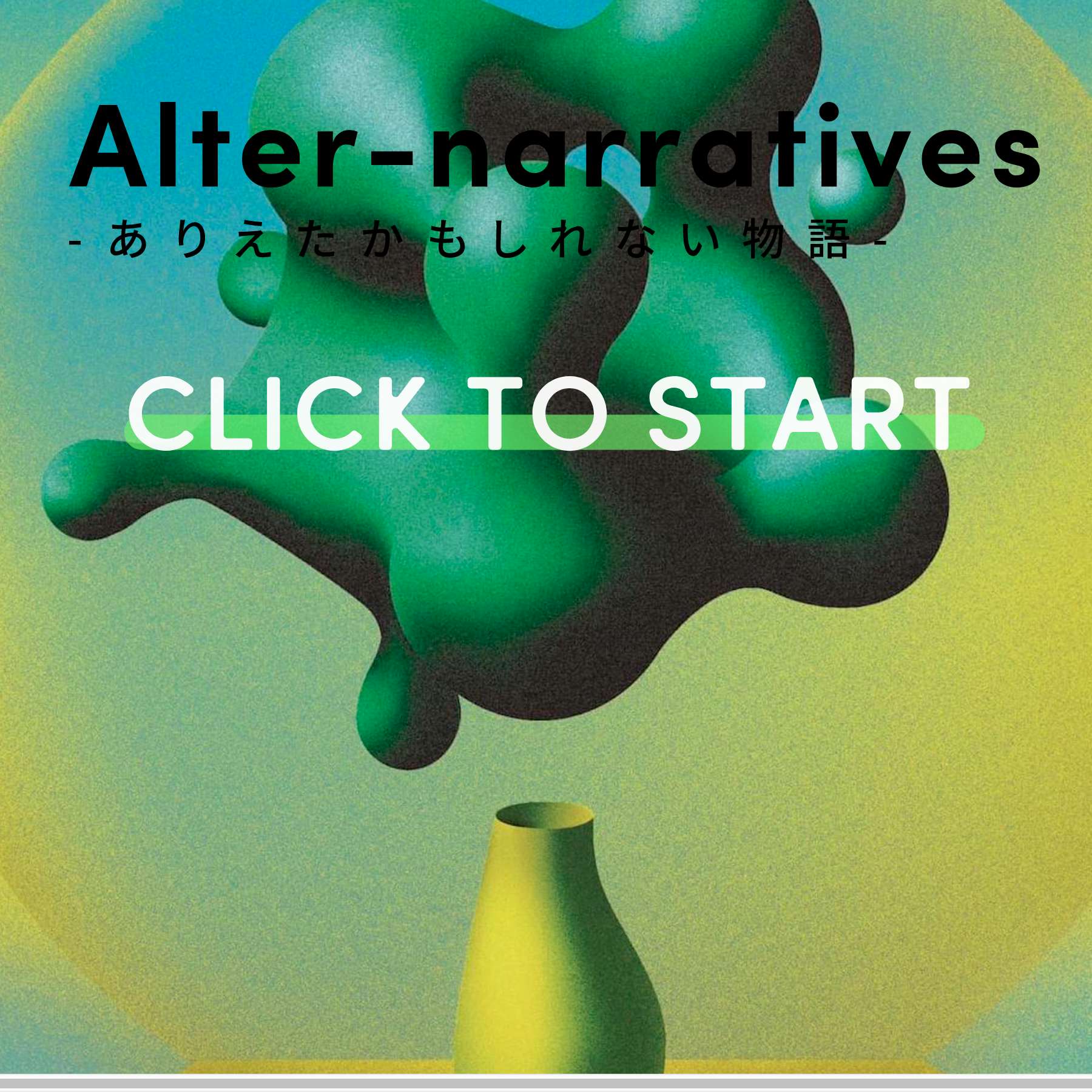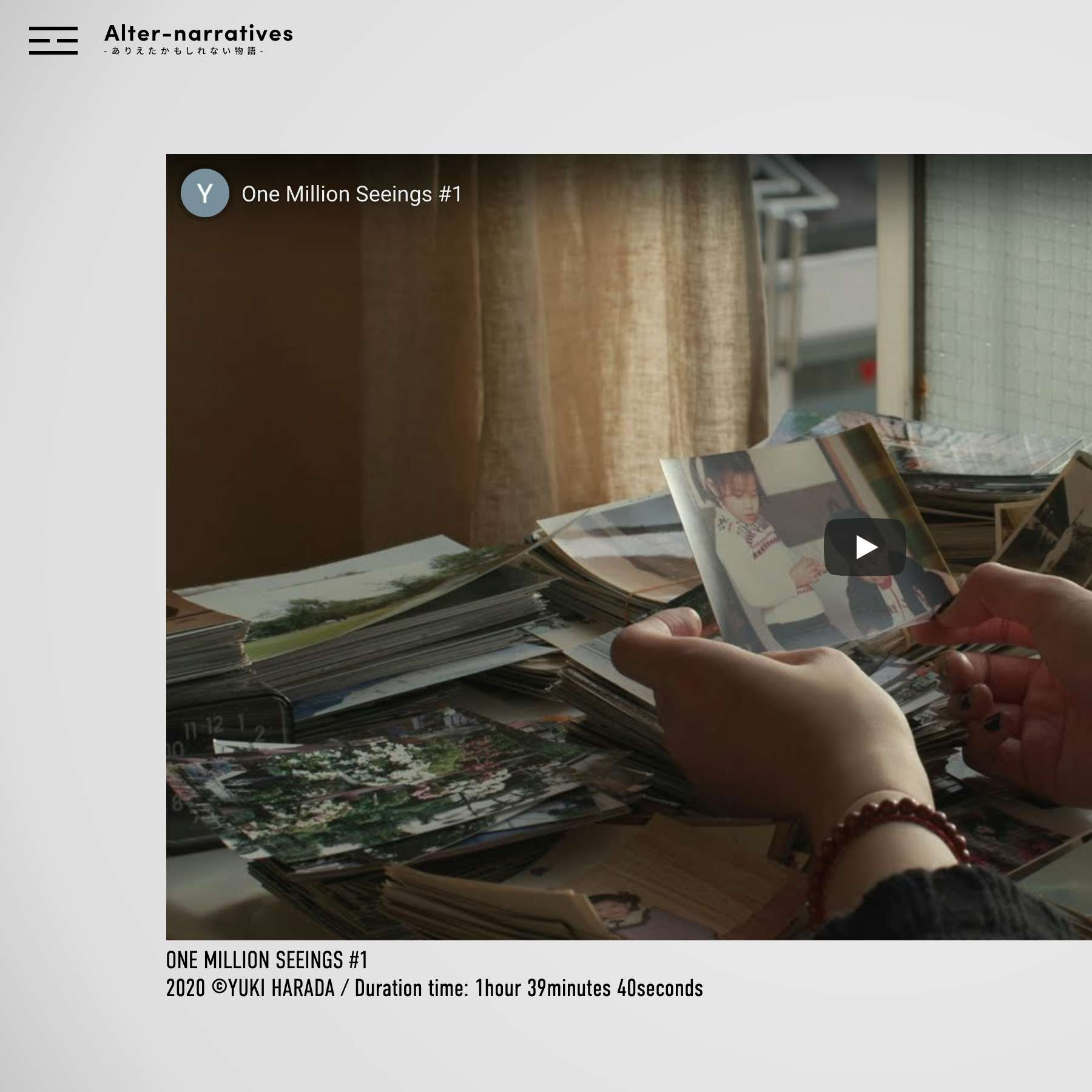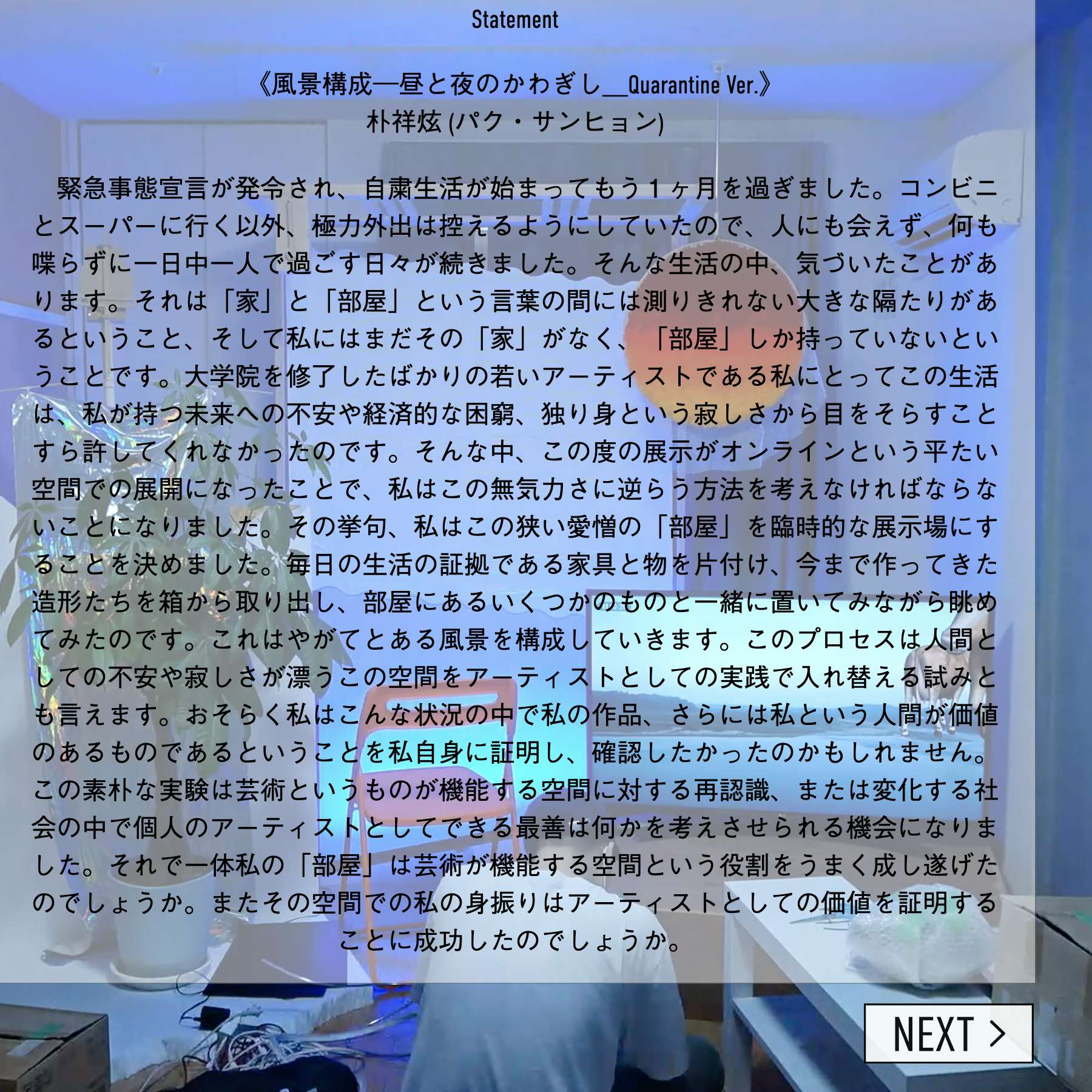現実を引き受け、超克する試み。山本浩貴評「Alter-narratives−ありえたかもしれない物語−」展
東京藝術大学大学院の国際芸術創造研究科が主催するグループ展「Alter-narrativesーありえたかもしれない物語ー」が、6月1日〜30日に開催された。コロナ禍においてオンライン上での開催となった本展を、文化研究者の山本浩貴がレビューする。

可能性の海における浮島、あるいは代理人としての倫理
「Alter-narratives−ありえたかもしれない物語−」展では、長谷川祐子教授による監修の下、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科に在籍する5名の学生(岩田智哉、原田美緒、鄭智秀、金秋雨、Jying TAN)が共同キュレーターを務めた。当初は大学内の陳列館を会場に想定していたが、コロナ禍の影響を受け、オンラインでの開催となった。

「ありえたかもしれない現実に思いを巡らせることは、私たちが生きる現在、また眼前に広がる未来に対して常に批判的な思考をもって対峙する必要性を再認識させます」。本展コンセプトから想起したのは、鶴見俊輔が埴谷雄高を論じた言葉だ。「可能性の海の中の一つの浮島として現実を見る」(*1)──鶴見は、その作家の世界観を評してこう述べた。
この鶴見(埴谷?)の感覚について、上野俊哉は次のように書く。「これは自分の土地や現場を掘っていくことで外とつながるトランスローカルな感覚であり、今日のグローバリズムとは全く異なる。(中略)これは「いくつかありえた自分/社会」に余分なロマンも反感ももたずに、今ここにあるそれを引き受ける構えである」(*2)。本展の意図に、拙速に若者特有のロマンチシズムや反骨心を読み込むことは控えたい。彼・彼女らは、「いくつかありえた自分/社会」に対して、「余分なロマンも反感も」抱いていない。では、「今ここにあるそれを引き受け」たうえで、私たちに何ができるだろうか?

現代世界には喫緊の課題が山積している。人種や民族に基づく差別、環境破壊、格差……。新型コロナウイルスは、こうした問題の存在を改めて私たちに突きつけた。頻発する危機の時代に臨み、しばしば私たちはこう自問する。「なぜ私が」、あるいは「なぜ(私ではなく)あの人が」と。後者の典型は「サバイバーズ・ギルト」と呼ばれ、「自然災害や事故などで人が亡くなったときに、同じ体験をした生存者が感じる罪悪感」(*3)を指す。
その裏返しが、傲慢なエリーティズムである。「いまの私が享受する特権は、自らの努力の賜物である」。ゆえに、「ある特定の人々が被っている苦境は、ひとえにその人の過去の怠慢に起因する」。「貧困の原因を本人の行動に(中略)一方的に求める」(*4)生活保護バッシングの背景には、こうした歪んだ自尊心がある。これらの両極を避けるように与那覇潤は「代理人の倫理」を模索する。「それは究極的には他の人がやってもよかったことだ。でも、自分が代理としてベストを尽くしている」──「そういうモラルのあり方」だ(*5)。
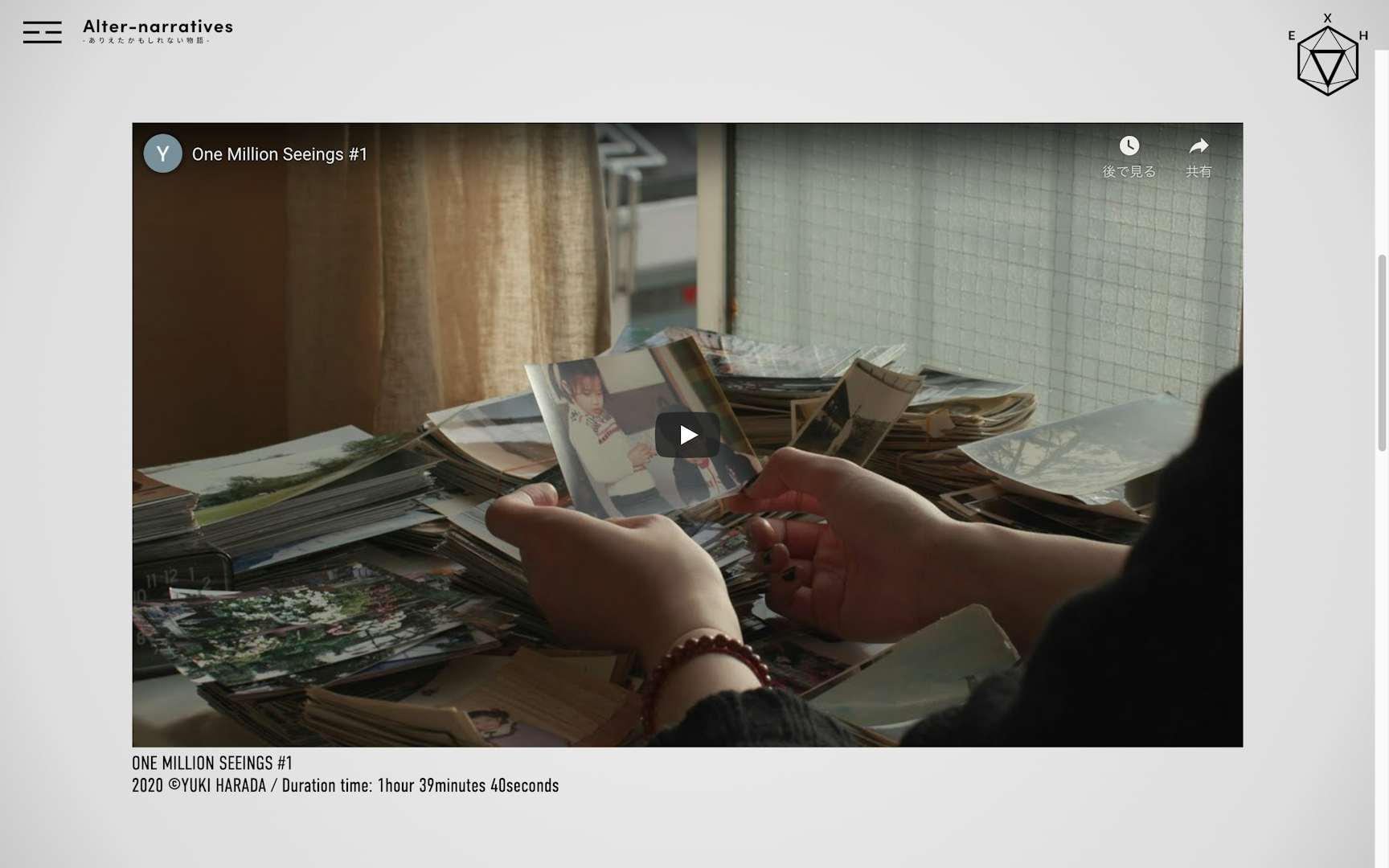
シングルチャンネルカラービデオ 1時間39分40秒
本展では、「代理人の倫理」として「可能性の海の中の一つの浮島」を可視化しようとするキュレーターやアーティストの姿勢が強く印象に残った。社会で周縁化されているものに繊細なまなざしを向けてきた原田裕規は、行き場を失った写真の記憶をさらい上げ、それを触媒に鑑賞者の眠った記憶を呼び覚ます。音楽家の七尾旅人は、『兵士A』を素材とした映像作品を学生とのコラボレーションを通じてつくり上げた。近い将来に起こるかもしれない戦争の最初の犠牲者を主人公とした『兵士A』のメッセージ性は、今回のコロナ禍を「戦争」と表現する指導者たちが支配する世界でさらに強度を増す。
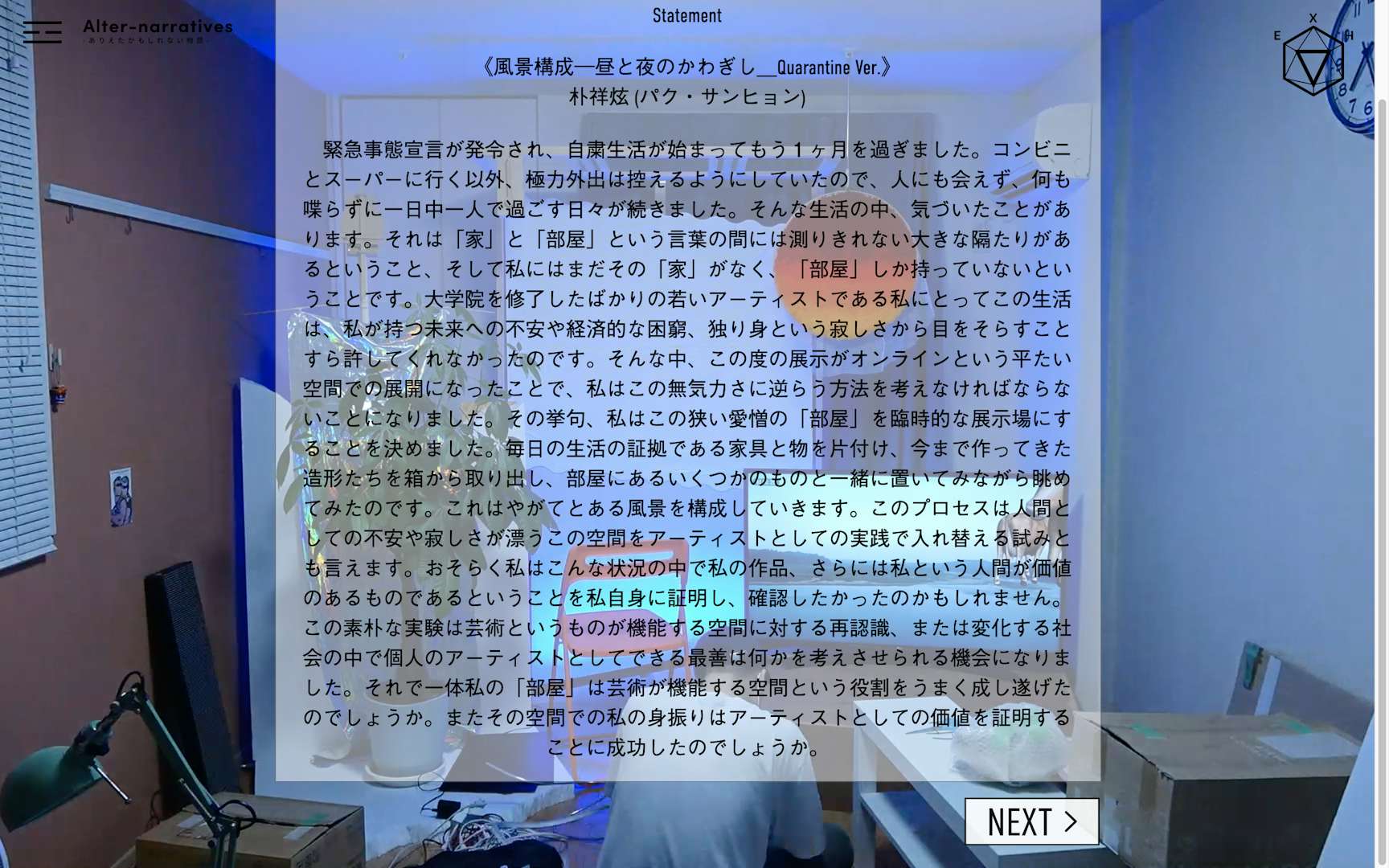
「トランスローカルな」本展が示すビジョンは、日本の文脈だけに紐づいていない。シンガポール出身のウェイン・リムは、テキストをベースにした作品を発表した。そこには「インドネシアがシンガポールによる土地買収の提案を拒否」など、妙なリアリティを帯びた虚構の物語が示された。北朝鮮から脱北した祖父を持つ朴祥炫(パク・サンヒョン)は、インスタレーション《風景構成》において、想像力を駆使して分断された南北朝鮮の壁を越えようとする。彫塑を専攻した朴らしい、来たるべき現実の「彫刻」であり、今ここにある現実の「超克」である。
精神科医の宮地直子は、戦争、災害、DVなど筆舌に尽くしがたい経験について語る可能性を模索するなかで、トラウマの「環状島モデル」を提唱している。その内海は「ブラックホールのようなものであり、誰もその中心にまで迫ることができない」が、支援を通じて「〈内海〉から証言者を〈陸地〉に引き上げる」ことで、難しい問題を言葉にしていく回路が開かれると彼女は主張する(*6)。「ありえたかもしれない物語」を探る本展の営みも、決して空疎な概念上の遊戯にとどまらず、現実的な可能性の回路へとつながっているはずだ。
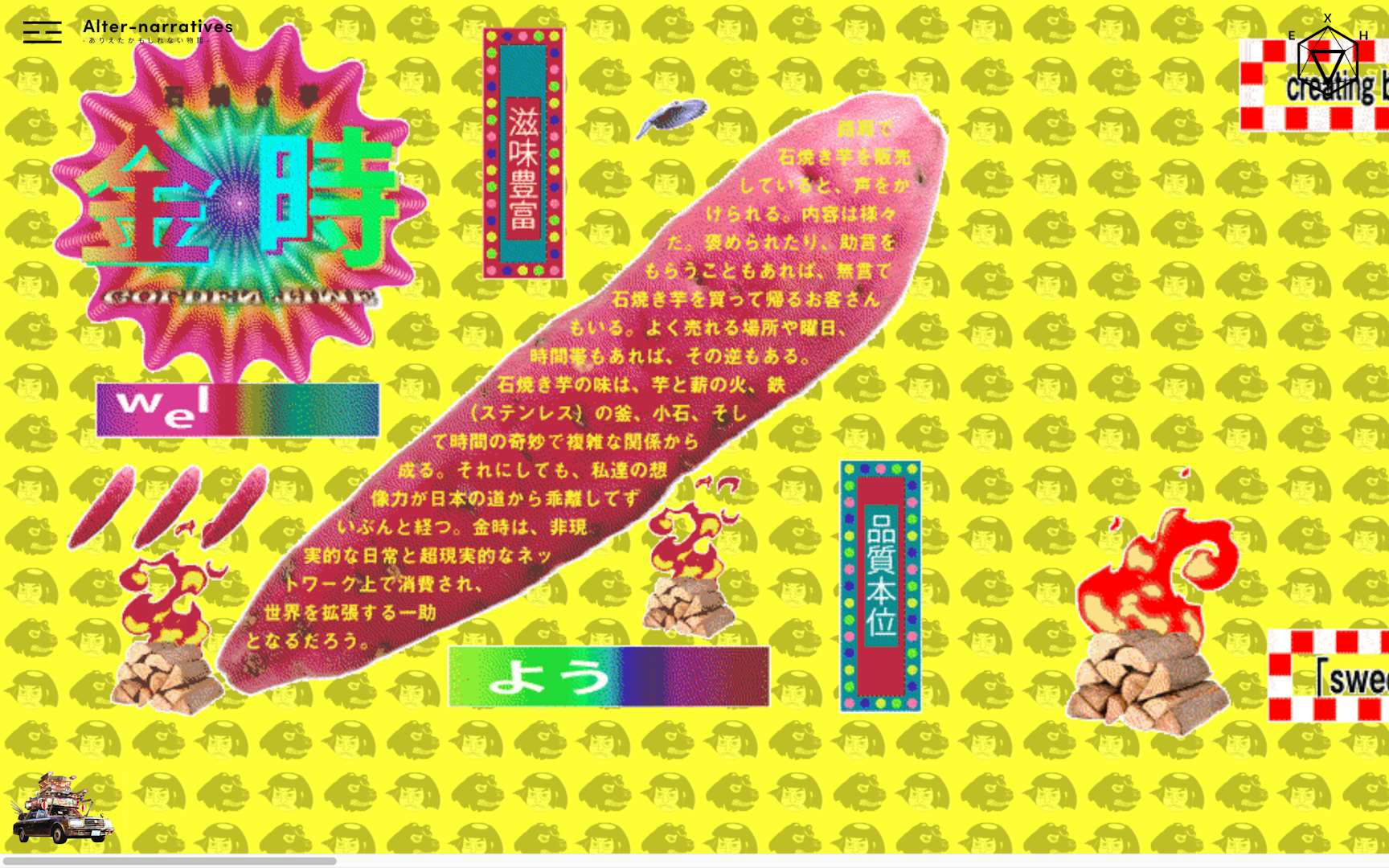
アフターコロナの時代におけるオンライン展という意味でも、本展は「可能性の海の中の一つの浮島」を探す試みであった。Yotta(木崎公隆、山脇弘道)の作家ページでは、一昔前のプログラミング言語が使用され、ノ・サンホのドローイングには焦点をぼかすエフェクトがかけられた(徐々にクリアに見えるようになる)。別会場に設置された鈴木美緒のインスタレーションを撮影した動画は、生身の身体では不可能な視点からの鑑賞を可能にし、ウィットに富んだ社会批評を得意とする田村友一郎は、ブログ形式を模したテキストの実験を展開した。
本展は2020年6月30日をもって閉鎖された(一部のコンテンツは引き続き閲覧可能)。一般にインターネットの利点とされる、コンテンツの半永久性や時空間を超えた観者の接続性といった要素は、本展ではあえて活かされていない。その点でも、「Alter-narratives−ありえたかもしれない物語−」展は、現代美術のオンライン展覧会の「ありえるかもしれない」可能性を愚直に探求している。
*1──鶴見俊輔著『埴谷雄高』講談社、2005、20頁。
*2──上野俊哉著『思想の不良たち 1950年代 もう一つの精神史』岩波書店、2013、26頁。
*3──松井豊著『惨事ストレスとは何か 救援者の心を守るために』河出書房新社、2019、139頁。
*4──橋本健二著『アンダークラス 新たな下層階級の出現』、筑摩書房、2018、58頁。
*5──与那覇潤著『歴史がおわるまえに』亜紀書房、2019、376頁。
*6──宮地直子著『環状島=トラウマの地政学』みすず書房、2007、9頁、17頁。