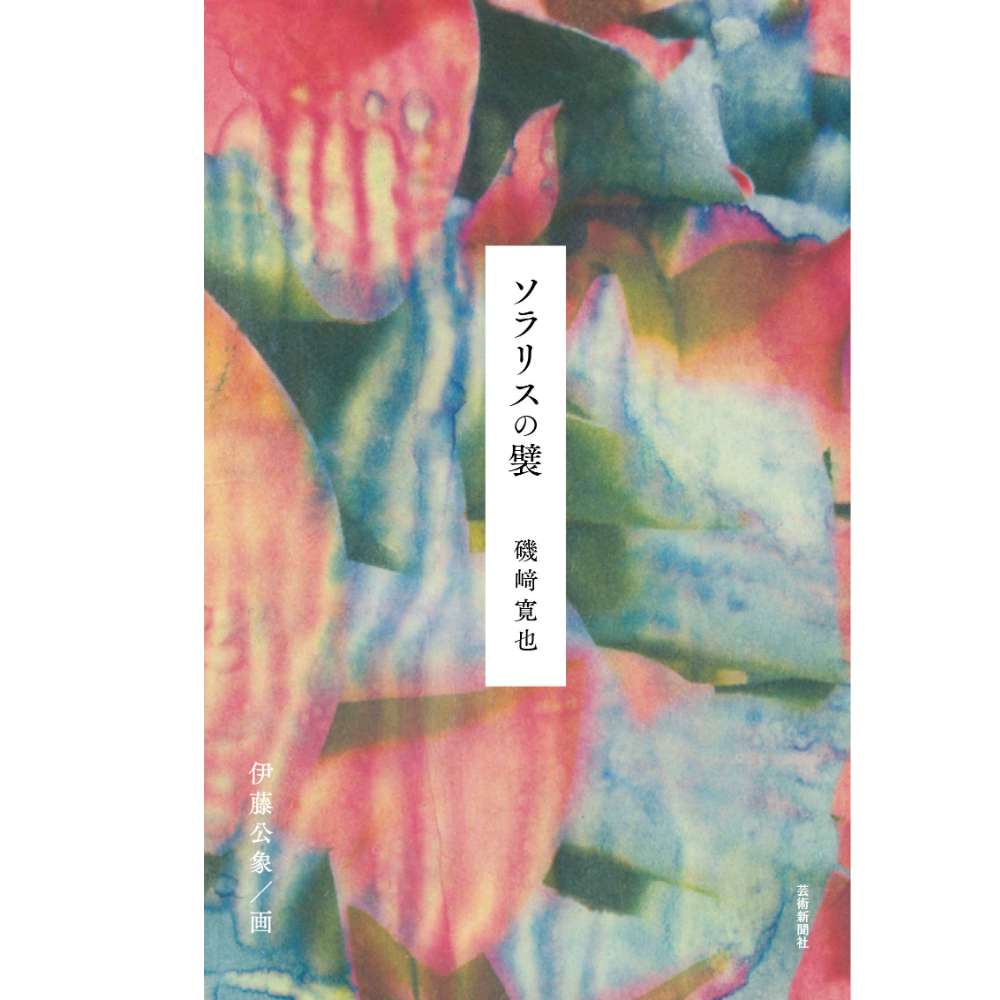ARTS ISOZAKIを主催するアートプロデューサーの磯崎寛也の詩集『ソラリスの襞』。磯崎が師と仰ぐ現代美術家・伊藤公象が挿絵を担当した本詩集はいかに誕生したのか。ふたりに制作にいたる過程や、伊藤の活動が磯崎に与えた影響などについて話を聞いた。
茨城・水戸でARTS ISOZAKIを主催するアートプロデューサーの磯崎寛也。2017年に大病を患い、生死の狭間を彷徨ったことを契機に、その意識は学生時代のような詩作へと向かった。
そこで磯崎の創作意欲をさらに掻き立てたのが、現代美術家・伊藤公象の存在だ。やがてその詩作は、詩を磯崎寛也が、挿画を伊藤公象が担当する詩画集『ソラリスの襞(ひだ)』(芸術新聞社)として結実した。茨城・笠間の伊藤のアトリエを訪れ、同書について、そして後世に伝えたいこれまでの伊藤の創作について、ふたりに話を聞いた。
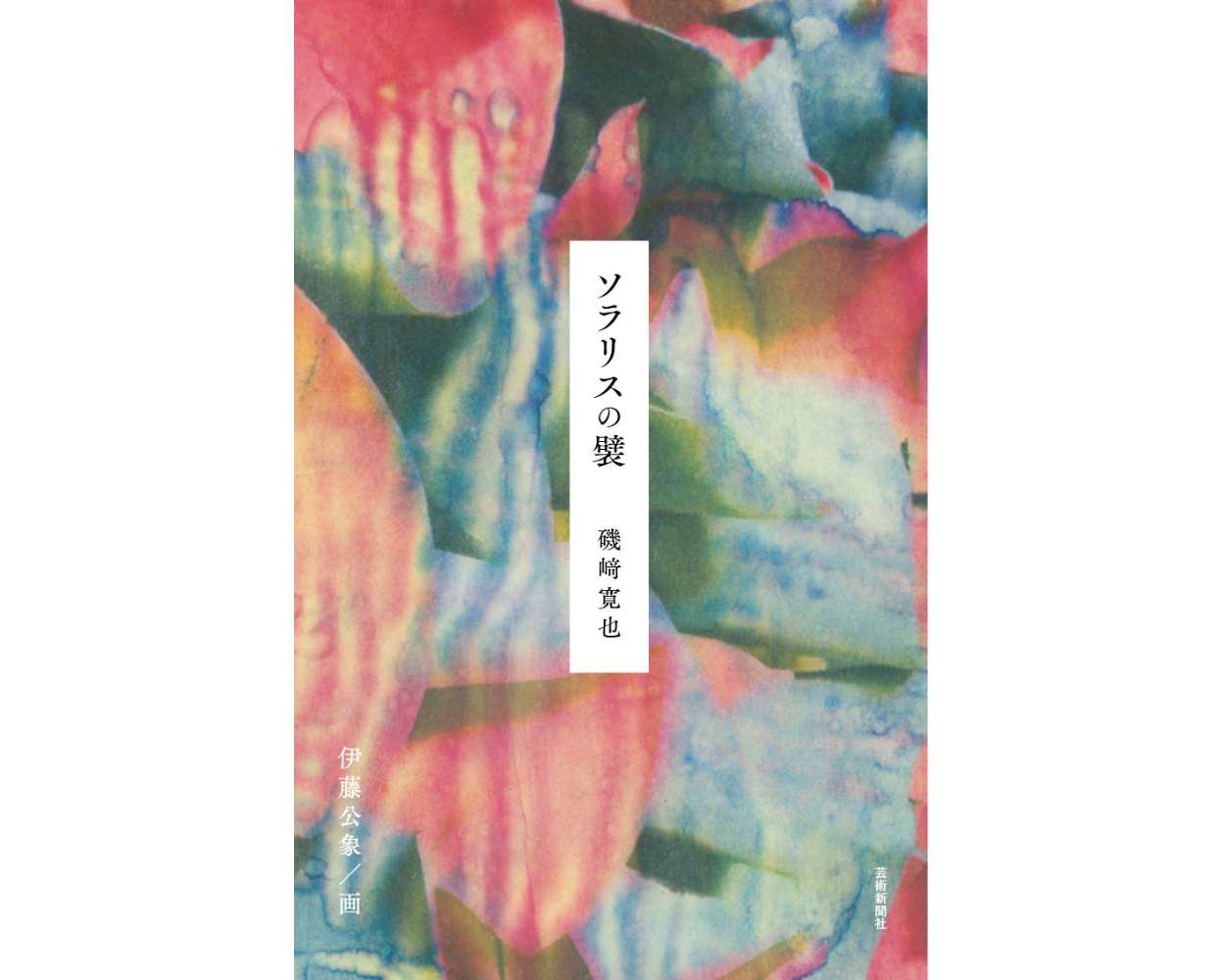
死と向き合って出会った詩作
──巻末に収納された「この詩集について」を拝読すると、磯崎さんを再び詩作へと向かわせた契機として壮絶な病床体験があったことが綴られています。化膿性脊髄炎によって脊髄に3つの穴が空き、「いつ退院できるか、治るかどうかもわからない」という医者の言葉を受けて入院、鎮痛剤によって朦朧とする意識のなか、激痛と闘う2ヶ月間を過ごされました。悪魔のような姿で幻覚となって現れる痛みの姿を書き留めることが、詩作の発端となったという描写に衝撃を受けました。
磯崎寛也 大学は文学部で、詩人になろうと思った時期があったのですが、じょじょに何を書いていいのかわからなくなり実業の世界に入りました。しかし、2017年から2018年にかけての闘病生活で死を目前にして痛みと向き合ったことで、痛みだけが生の実感を確認できる要素であると感じ、その感覚が自分を再び詩作へと向かわせました。
病院では毎日詩を書いていたのですが、痛みが人格を持って姿を現すような幻覚的なものを見ていたので、その様子を書き留めたり、あるいはそれについて調べたメモを詩にまとめるなどして、100篇ほどの詩を書きました。それが詩作の発端です。ただ、その状態で詩集にするには至らず、放置していましたが、退院して伊藤先生との再会があり、先生の作品からイマジネーションが湧いて再び詩を書くようになりました。

──磯崎さんが水戸駅からほど近くに現代美術ギャラリーのARTS ISOZAKIをオープンされたのが闘病後の2018年秋でした。ギャラリーのオープンをきっかけに伊藤先生と再会されたそうですが、そもそも最初に出会ったのはいつのことなのでしょうか。
磯崎 アート関係の仕事で東京に住んでいたのですが、2002〜03年頃に地元で現代美術を根づかせる活動ができないかと茨城に戻ってきました。そのころ、茨城を拠点に活動をしている非常に高名な現代美術家がいらっしゃると知り、水戸芸術館で継続的に活動している日比野克彦さんらと一緒に、市民向けに伊藤先生のレクチャーを企画して開催する機会がありました。伊藤さんには「クリエイションとは何か」「創造的な生き方とはどういうものか」というテーマで話していただきました。
このレクチャーをきっかけに先生の作品に触れるようになり、アトリエにお邪魔して作品を購入もさせていただくようになりました。私にとって伊藤先生はアートの先生です。また、ご家族と茨城の笠間に拠点を築き、創作活動を続けながら自分の世界を生きるという、人としてのロールモデルのような存在で本当に尊敬しています。
──詩画集のタイトルには「襞(ひだ)」という単語が用いられ、そこには伊藤先生の作品からの大きな影響を読み取ることができます。
磯崎 20世紀フランスの哲学者であるジル・ドゥルーズの『襞』という本がありますが、その発想の根本には17世紀の数学者で哲学者のゴットフリード・ライプニッツの「モナド(単子)論」があります。端的に説明すると、力には様々な種類、方向、質量があり、それがあらゆる物質に働きかけることで襞ができます。その襞は〈物理言語〉と表現できるものかもしれません。その複雑さは人知を超え、そうした無数の襞によって宇宙は構成されていて、そうしたことを考える人間もその襞の一部だということができます。伊藤先生も長く世界をとらえるための要素としてモナドや襞を創作テーマに据えられていて、私も世界をもう一度読み解きたいという思いで詩の世界に入ったので、詩画集のタイトルに「襞」を用いらせていただきました。

──「ソラリス」という語は、タルコフスキーが『惑星ソラリス』として映画化したスタニスワフ・レムの小説『Solaris』(1961)からの引用ですね。
磯崎 そうですね。地球外の惑星を舞台にした小説ですが、そこには意識を持つひとつの生命体として「ソラリスの海」が描かれていて、世界全体を襞としてとらえる世界観と親和性を感じ、このタイトルを名付けました。収録した個別の詩の中でも、「雰囲/化粧」「時間の褶曲」「起土と喪失」「木の肉 土の刃」「Q/多軟面体」など、いくつかの詩には伊藤先生の作品タイトルを引用させていただきました。
伊藤公象、その創作が与えるもの
──昨年秋から今年の3月までARTS ISOZAKIで開催された伊藤先生の個展「ソラリスの海《回帰記憶》のなかで—In the sea of Solaris」では、建物の複数のフロアと屋上を使用してインスタレーションを展開されました。モナドを構成する低層と高層の2層構造なども、建物全体を使ったインスタレーションに表現されていると感じました。
伊藤公象 モナドに始まる襞という概念を私はずっと持っているので、陶を用いたインスタレーションでそれを見てもらいたいと思って制作を続けてきました。2016年に開催された「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」に《pearl blueの襞 —空へ・ソラから—》という作品を出品したのですが、それを水戸の街中にあるARTS ISOZAKIの高いビルに囲まれた屋上空間で展示したら、素晴らしいインスタレーションになるとイメージしました。街全体の景色の一部となり、太陽が当たり、天候が変わり、雨が降ることで変化し続ける。それを小さなビルの屋上で、何十年経っても消えることのないブルーパールの発色から生まれる光景を多くの人に見てもらいたいと考えて、あのインスタレーションは生まれたのです。
──伊藤先生は1972年に、アーティストであるパートナーの伊藤知香さんと笠間に引っ越し、アトリエを構えられました。陶を用いた制作はそれ以降だと思うのですが、表現活動を行うようになった経緯をお聞かせいただけますか。
伊藤 私は12歳のときに父(編集部注:彫金家・伊藤勝典)を亡くしているのですが、戦時中で金属は統制され、火箸や火鉢、五徳まで金属を提出、父は制作ができなくなりました。その父の無念を継ぎ、父のぶんまで制作をという想いが今も強いのです。一家の支柱をなくした戦後、母は7歳の次女を養女に、5歳の次男を養子に出し、学童疎開の寮母になって長男の私を父の知人で板谷波山の流れを汲む陶芸家に弟子入りさせます。そこで5年間、陶器の成形や、原型、釉薬の融合、登り窯造りなど、陶芸の基礎を身につけました。
ただ、当時の陶芸の主流だったのは、陶磁土で花器などの形をつくりそこに絵付をするという技法や技術。それが優先されることに疑問を持ちました。そこで美術批評を勉強しようと考えたのです。

──美術学校を目指されたのでしょうか。
伊藤 いいえ、富山県の地方新聞社に飛び込んだんです。政治部や社会部などを経験して、あらゆる出来事を自分の目で見ようと考えました。例えば、電力会社がダムをつくり、それによって崖崩れが起きる危険が生まれたとしましょう。地元の人は、崩れてしまう前に補償してくれと掛け合います。すると電力会社は、地質学者を立てて地盤はしっかりしていると主張する。そこに地元の政治家が入ってくる。また別の地質学者を連れてきて、地盤は脆いから補償が必要だとなります。どちらがいいのか、自分の目で見てもわかりません。いや、よく見ても本質というのは簡単にはわからないのかもしれない。新聞社でそんなことを学び、批評の目を持つ作家になろうと、5年で退社して裸一貫でアートを志すようになりました。

──最初はどのような素材や技法で制作を始めたのでしょうか。
伊藤 最初は木彫をやっていて、団体展の木彫部門に出展したこともありました。しかしそこでは「彫刻とはこうあるべき」という概念があって自分には向かないので、退会して貸し画廊で個展をやるようになりました。そのときは面識もない批評家のヨシダ・ヨシエさんが見にきてくださって『美術手帖』に展評を載せてくれましたね。
東京時代、現代美術の画廊まわりをしていて、現代美術の作家や美術評論家と会いながら現代美術に触れると、木彫をやっていることに違和感が生まれてきました。有機性について志向が強かったので、木の木目(年輪)それ自体が有機的な意味を持ってきてしまう。それで木彫をやめようと決めました。ただ、カンナの削り屑の透き通るような美しさは、いまの土の造形に大きな影響を与えています。そして、再び土の造形をと、笠間で妻と工房を持ちました。1972年の夏です。
やがて現代美術の北関東美術展で大賞受賞、インド・トリエンナーレ国際美術展やヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展に推薦出品するなど、土の造形活動が始まりました。
土をこねて焼き、集合させることで作品にしようと考えたのが1972年に笠間に来てからです。それから北関東美術展で賞をもらってインド・トリエンナーレに出してもらったり、東京の個展を見た評論家からヴェネチア・ビエンナーレに呼んでもらったりと、笠間で作陶をするようになってから仕事を続けられるようになりました。

──笠間でこねて焼成された土が、都内のギャラリーや東京都現代美術館、芸術祭などでインスタレーションとなり、多くの人から注目されてきました。そして2019年にARTS ISOZAKIで「土の襞」展が開催されてから、磯崎さんにとって伊藤さんの作品はさらに大きな意味を持つようになってきたのでしょうか。
磯崎 アトリエにお邪魔して伊藤先生の作品を見させていただくうちに、作品にインスパイアされて私が制作した詩や絵を、先生に見ていただくやりとりが生まれるようになりました。表に出すつもりはなかったので、あくまでも先生にお伝えしたいという思いで続けていたんですね。あるときに先生から詩集を出したらどうかという話があり、恐れ多いとは思ったのですが、半分冗談で「先生が挿絵を描いていただけますか」と申し上げたところご承諾くださったんです。
伊藤 私は批評家ではないし、詩への造詣が深いわけではありませんが、磯崎さんの詩にはイノベーティブなものを感じます。社会を改革していくんだという、そういう気持ちが根底にあるからあのような詩を書けるのではないでしょうか。だから詩集を出したほうがいいとお薦めしたわけです。
そのときは挿絵を描くことは想定していませんでしたが、磯崎さんから挿絵のお話をいただいて、考えてみました。独学なのでデッサンなどを正式に美術学校で学んだわけではないけど、現代美術の観点から、もっと新しいドローイングが自分なりにできるのではないかと。一種の覚醒ですね。磯崎さんとの出会いによって覚醒があったわけです。
磯崎 私の詩に関しても、最初は病院で書いたものをしばらく放置していましたが、伊藤先生との再会があり、作品を拝見するたびにイマジネーションが湧いてくるようになったので私にとっても覚醒と言えるかもしれません。最終的には、病気で死に接近したことで感じた生への希望と、伊藤先生の作品から自分のなかで湧き上がったイメージみたいなものとが入り混じるかたちで、40篇ほどの詩になりました。書くことによって視野が広がり、色々な土地を訪れて喚起された伊藤先生の作品のイメージが結びつけながら詩を紡いでいきました。絶望から生きる希望に至るまでの5年間の私の精神の変遷を表現したいと思いました。それが伊藤先生の作品と合わさり、生きる希望として広く伝わればと思っています。

詩画集『ソラリスの襞』で伝えたいこと
──そして伊藤先生の初のドローイング作品が、詩画集『ソラリスの襞』に掲載されることになりました。文字通り、色鮮やかな襞の陰影も取り込んだ美しいドローイング作品は、1年の試作を経て生まれたと聞きました。制作技法をお聞かせいただけますか。
伊藤 私のパソコンには8000枚ほどのこれまで撮影した画像が入っているので、それを選んでプリントすることから始まります。支持体となるのは薄い無地の新聞紙です。そこに粘土の板を置いて、乾燥して収縮すると襞が生まれます。1点1点その襞の様子は違うんですよ。木の台の上に紙を載せた場合とガラスに載せた場合とでも変わりますし、粘土の水分や重さなどでも変わってくる。土と水という自然の力を借りてどんな絵が生まれるか、テストを1年ほど続け今回の技法が生まれました。1980年代から制作している「褶曲」という仕事のシリーズがあるのですが、それを展開してドローイングにしたのが今回の作品です。

──この詩画集がどのような人に届けばいいと思いますか。
磯崎 いまクラウドファンディングで伊藤先生の作品集をつくっており、そちらとセットで、全国の美術館と美術大学に寄付する予定にしています。セットで手に取っていただいて、とくに若い人たちに伊藤芸術を知るきっかけになってほしいと思っています。
大袈裟な言葉になってしまうかもしれませんが、ポスト資本主義ということを考えていて、資本主義によって失われたものを取り戻すきっかけが伊藤作品にはあると思っています。それはひとつの魔術的なものであったり、世界のとらえ方であったり、お金に換算できないものです。伊藤先生の作品には、経済システムによって定量化し交換することができない、現代人が見失いがちな何かがあると確信しています。
──アートを体験することが必要な理由を考えさせてくれることに大きな意味がありますね。
磯崎 先ほど先生がカンナで削った木の皮の話をされていましたが、それを美しいと思ったとしても、そこにお金の価値を見出すわけではありませんよね。しかし、作品にすることで、美が自分たちの喜びにつながることを明らかにしてくれる。時間をかけて伊藤先生の作品を見ていると、今まで見たことのない自分が見えてきたりします。瞑想、メディテーションという言葉になるのかもしれませんが、アートと触れることによって、普段の直線的な生活と離れて、自分を解放することも可能になるのではないでしょうか。伊藤先生の作品がその入口になってくれればいいなと思っています。
伊藤 詩集も作品集も若い人に見てもらえたらいいですよね。感覚で見てくれる若い人が何かを感じてくれたらいいですし、磯崎さんの詩も非常に内容が深いので、どこまで理解されるかではなく、そこに何を感じられるかを大事にしてもらいたいですね。