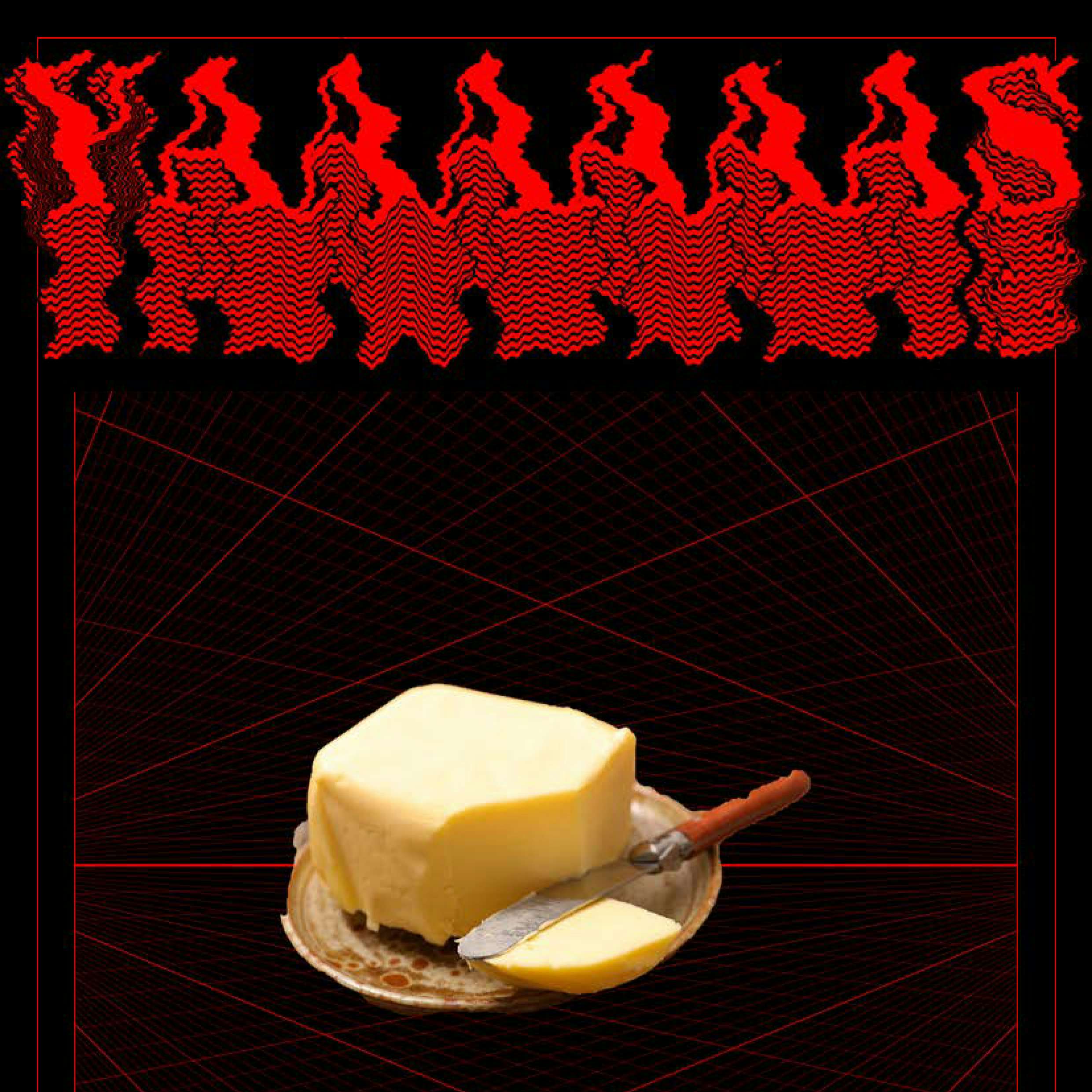ポスト資本主義は「新しい」ということを特権としない Vol.1:卯城竜太(Chim↑Pom)
いま必要なのは、「ポスト資本主義」ではなく「ウィズ資本主義」だ──。道具やスペースのシェア、見返りを求めない贈与的な活動、プロジェクトを通じた異なる階層の出会いの創出など、アートはそもそも経済的価値では測れない独自の芸術的価値を生きてきた。ひとつのシステムに「包摂」されない、こうした脱中心的な態度は、経済体制だけでなく、作家活動における「展覧会」の相対化、真に多様なコミュニティへの志向、人間を超えた「サブジェクトの多様化」など、アートの世界にさまざまに現れ始めている。「美術手帖」本誌10月号で「ポスト資本主義とアート」をめぐる対談に臨んだChim↑Pomの卯城竜太が、そこで語ろうとした思考の全容をあらためて綴る。

はじめに、いくつもの世界があった
「ポスト資本主義」の妄想癖がいつからあったかを考えると、きっかけというきっかけが思いつかない。家庭環境が人より左寄りだったからか、資本主義というものが一種のシステムであり、有限であるようなイメージは幼いときからあった。そして、10代の反抗期にはむしろどっぷりと市場経済のトレンドに浸かり、「生まれは共産主義」ながら「資本主義育ち」といった真逆の価値観で人間ができてしまった。
思えば僕にとってのデビュー展「こたつ派2」(会田誠キュレーション、ミヅマアートギャラリー、2004年)で、何巻かの『資本論』の背表紙に「ナリアガレ万国の労働者」と落書きした雑なものを展示したが、あれがこの問題の私的な原点であり、つい重たく見がちだったイデオロギー論というものから自分をズラした曲り角だった。
そんなわけで自分の認識としては、資本主義もしかり、この世のすべては意外とモロく、遅かれ早かれ変わりゆくものだ。だから有事になっても、絶対的な社会が壊れたように感じたことはなく、盤石に演出されてきた書割が露呈した、くらいにしか思わない。そういう意味でも、逆に「普遍性」こそがコアであるアートに出会えたことはラッキーだった。
中流階級の安定神話が崩れ、貧困が定着してきた頃だったろうか。そもそも労働力を商品として生きること自体がどうにもこうにも耐えられず、バイトも長くは続かなかったのだから、社会を語る以前に、性格に応じた進路だったのだろう。ただ、まあ、これがアーティストになった理由だというのは珍しくもない。なんなら動機としてはありふれている。そんな資本主義的やる気に欠けた奴らばかりが集まっていたわけだから、むしろアートと安酒を媒介に、自分の半径100メートルくらいに脱資本主義的な世界を構築することは楽勝だった。
が、当時は同時に、世はアートバブル全盛期。それはそれで、何かエクストリームな存在感でアートはある種の凄みを世界に醸し出していた。「本当に同じ業界なのか?」と目が眩むようなその両極がもたらすアートのダイナミズムに、僕は、自分の「生まれ」と「育ち」の不一致に通ずるものを見たのだろうと思う。
「包摂」から隠されたもの
格差と環境問題が深刻化した現在、その主な原因と言われる新自由主義への批判として、ポスト資本主義の議論が高まっている。
「我亡き後に洪水よ来たれ」──。これは、マルクスがノアの方舟にちなんだポンパドゥール夫人の言葉を引用して例えた、資本主義の本質であり、新自由主義の本音だ。大洪水が来るとしても、それ以前に自分が儲けられていたら、後は野となれ山となれ。その引き金が自身に由来したとしても。このリアリティは年々増していて、文字通り洪水だ台風だと災害が多発する環境問題はもちろんのこと、1パーセントの富裕層が99パーセントを搾取する格差社会に照らしても、肯く人は多い。
しかし逆に、そう思わない人も多い。稼げないのは自分の力量でしょ、なんて自己責任論がまかり通るのは、資本主義がドープになるにつれ、個人の考え方や行動原理、感性が資本主義の論理に「包摂」されるからだとの見方がある。マルクスは「包摂」を、労働現場の規則正しい再編成などにより、労働者が従順になるといった意味で言ったらしいが、現在は工場からさらに社会全体に広がり論じられている。たとえば、自己責任論の行き着く先というか、自分の価値を高めようとオンラインサロンやビジネス書に投資する、その「資本主義化された」個人のマインドなどがそれだ。
結論から言うと、僕はこの「包摂」をめぐる見方を正しい分析だと思っていて、しかしそれは社会主義であれ、民主主義であれ、ファシズムであれ、同じことが言えるとも思っている。要は、対象が何であれ、最低でも僕は、組織や体制の論理を内面化しちゃう「個」も、それを必要とするような「公」も、嫌いなのだ。現在におけるアートの意味は、本屋に並ぶ「ビジネスに使える!」ような教養にではなく、世の中にあるあらゆる思い込みからの自由にあって、ビジネスにはむしろ邪魔になる。だからこそ、資本主義からの本質的な脱却も、その先にしかないと思うのだ。
例えば学生運動が華やかだった頃、資本主義には疑問を呈しつつも、集団の熱のなかで「運動」の論理に包摂されていた人も多かっただろう。資本主義の「後」について話していたって、また次の別の主義が同じように個人を扱い、個人もそれを求めるならば、そんな発想にはまったく魅力を感じない。そんなメインストリームの下克上よりも、むしろストリームで言えば、すでにある小さなフリンジ(周辺)の可能性に論点が移せないだろうか、と思う。
新たな発明を待たずとも、資本主義に同化しなかった存在やセオリーは無数にある。先住民の文化やアンダーグラウンドカルチャー、フェミニズム、アートだってその一種だと思うけど、そのバリエーションが遠慮なく繁栄するプロセスにこそ、資本主義による「包摂」がオワコン化し、オルタナティブなシステムが社会に実装される道がある。そして、そうなればむしろ資本主義も、そうしたさまざまな価値観の選択肢のひとつとしては、意外に有効なツールなのではないかと思う。
「包摂」の最たるブレインウォッシュは、その価値観が唯一のものとして無意識にまで定着してしまうことにある。そうなると、「資本主義」で言えばこれは絶対的な世界と思われるわけだから、その次なんて想像できないか、あるとしたら、何かとんでもなく新しいものか、と想像力が麻痺してしまうのだ。「資本主義の終わりを想像するよりも、世界の終わりを想像する方が容易い」みたいな言説だって、むしろ資本主義に組み込まれたイマジネーションだな、と思う。

「ウィズ化」という世界への向き合い方
「ポスト資本主義」──。ところで、この言葉にはずっと違和感があった。
「歴史の終わり」までは、その後は社会主義であり、共産主義であり、アナキズムであり、イデオロギーが「その後」の体制として想像されていた。冷戦後にこれが茶番になったような雰囲気と、でも資本主義の矛盾が社会に深刻なダメージを与えることへの待ったなしの対処として、面倒な論争は先送りにされたのだろう。「とりあえずポストで」という仮のニュアンスを感じるわけだけど、なんだかアーティストにお馴染みの作品タイトル「仮題」のようだ。
それくらいには「ポスト」は使い勝手が良いから、コロナにもモダンにもヒューマンにもインターネットにも、とにかくこれまであらゆるところで多用されてきた。それでもやっぱり世の中的にはポスト資本主義と言った時点で、「そんな世の中あるのかな......」と頭が真っ白になるのがつねで、「後」という響きは相変わらず議論を噛み合わせない。どうも資本主義がきれいさっぱり無くなった後の話をしているようで、目が点になるのはなぜだろうか。「ポストインターネット」にネットが無くなるなんて極論は装備されていないし、「ポストヒューマン」と言ったら尚更のこと......。
などと、相変わらずの浅慮で沈思黙考、酩酊していると、テレビからの啓示。コロナ禍に、なんと小池百合子さんからひとつのヒントを授けられた。今年3月、まだコロナが目新しく、「戦争」すべき相手と叫ばれていた時期には、それを撲滅した以降を「ポストコロナ」と呼ぶ識者が多かった。が、ゼロにするのが厳しいとわかった途端に、じゃあどう付き合っていくかと、「ウィズコロナ」に言い換えられた。もはやお馴染みの標語であるが、なんと言ってもその見切りの早さ。これがいくつもの政党を渡り歩いてきた人間の適応能力かと感心したが、インスパイアもあった。
端的にいうと、「ポスト」ってより「ウィズ資本主義」かもしれん、的な。つまり、資本主義もそんなもので、いまは主役として盛大にドライブしているから、誰も彼もが「資本主義オンリー」の価値観で物事を考えてしまう、そう頭が訓練されてしまっているけれど、その脳味噌に「ポスト」があり得ることをインストール出来るのは、机上の啓蒙ではなく、コロナと生きる生活のような、実態としての資本主義の「ウィズ化」なのではないか、と。
べつに、イデオロギー論を否定しているわけではない。ただ、僕にとっては「大きな物語」を語る以前に、いかに資本主義もその後の主義も「ウィズ化」できるか、その気楽さが包摂への免疫として重要なのである。「僕にとって」と言ったが、いっそ「アーティストにとって」と言い換えてみたい。アートシーンとは本来、ごった煮の生態系であり、善悪や一般の基準にならった構成とはまた別の独特さを持とうとする。オールジェンダー、オールアイデンティティ、スラムから超富裕層、そしてあらゆるオリジネイターまでをも内包しようとするアートは(もちろん現実がそうなっているとは言わないが)、それらすべてを「ウィズ」として、アートの名の下にしかヒエラルキーやホラクラシーを成立させない。
いっぽう、そんな理想論を楽観的に語っているだけでは意味がない、という残念な状況が業界に露呈しまくっているのも事実である。属性だけで無根拠に低く見積もられる人がいる限り、彼女ら、彼らは戦わないと「ウィズ」にもなり得ないし、権威側も無自覚なままである。フェミニズムや人種差別への抗議が男性や白人中心主義の呪縛......包摂から人々を解放し始めている現状は、近代のシステムがいかに根深く、しかし控えめに言っても革命的と言いたくなるうねりの前では、意外とモロいことを示している。
アートとポスト資本主義
アートとは、その天然において、そもそもポスト資本主義的なものである。むしろポスト資本主義が、アートの天然のようなものかもしれない。どちらが先かには何の意味もないが、たとえば、シェアリングエコノミーなんて言葉が出るはるか前から、アーティストは道具や人材や労働を共有し続けてきた。なかでも特筆したいのは、シェアアトリエ、シェアスタジオ。アーティスト・ラン・スペースともなり、コミュニティとしての性格をあわせ持つ。仕事と言えどもやはり趣味性が強いこの現場では、だからこそ共有や贈与が日常的に行われている。
コロナ禍にもかかわらず、新大久保の「UGO」とか西荻窪の「トモ都市美術館」とか、東京には新しい魅力的なアーティスト・ラン・スペースが増え続けている。あらゆる美術館やギャラリーがクローズしていた今年の5月や6月には、そこにお邪魔して遊んだりした。家ではないけど、店でもないし、ギャラリーとしても不十分。だから自粛要請の範疇でもない。そういう感じでアート・コミュニティは、これまでも独自の経済圏と文化圏を、社会に実験的につくり出してきた。
ほかにも、ギャラリーが展覧会を一般に無料で公開すること、芸術パトロネージュ、芸術祭のボランティア活動なんかも、資本主義の枠組みからは外れる「贈与経済」の一種だろうか。美術手帖本誌での対談を経て、ほぼノーギャラで書いているこの原稿も、ある意味そうだろうか。それとも、自らやりがい搾取に身を投じているのだろうか......。
アートと資本主義と言うと、欲望丸出しのアートマーケットへの批判がまずは浮かぶ。でも、そんなマーケットのあり方が、それがたとえばトモ都市美術館やUGOみたいなバラック・コミュニティ(なんて言葉はないが)にまで、悪影響を及ぼすのだろうか。コレクターやパトロンの一助を受けたとしても、投機が第一目的の怪しい金持ちとは距離を保つ作家は多い。むしろ、シーンを批評的にリードしている若手アーティストにとっては、売ったりなんだりという資本主義的な活動の方が、難しいという逆の実態すらある。極論を言うと、事業の継続や規模拡大さえ望まなければ、資本主義に活動が翻弄されるなんて、いまのところは稀なのである。
例えば、昨年の「あいちトリエンナーレ」での一件を受けて、出品作家であった僕たちが立ち上げた「ReFredom_Aichi」がクラウドファンディングで活動資金を捻出できたのは、ムーブメントへの応援があったためだった。最近、ワタリウム美術館がコロナ後の経済的支援を求めて募ったクラファンを圧倒的な人気で成功させたのも、救済という一時的な大義があってこそだ。そんな移ろいやすい衝動を定期的な収入にするのは、結局、なかなか難しい(そういえば、あいトリ騒動の際に文化庁のクソな態度を見て、僕や演出家の高山明さんは「新文化庁」というプランを夢想したけど、これも2年目からの資金繰りを考えると面倒臭くなった)。
つまり、資本主義的ではないモデルがアートシーンには登場しやすいいっぽうで、規模が拡大するにつれ、主催者や運営者には自ら資本の論理を求める必要が出てくるし、システムも入り込んでくる。また、それがビジネスチャンスともなれば、貪欲な資本主義はガッツリとそれを吸収しようとする。マーケットが巨大になり、その需要に合わせるように作品を作る作家が多くなった中国のアートシーンの一部や、シェアリングエコノミーと言いながらUberがドライバーを搾取して大儲けするのと同じ話である。
経済的価値は、唯一のものか?
巨大マーケットとの付き合い方はどうあるべきか。これは、アーティストが各々に態度を持つべきトピックだけど、はたしてその設問は、過度に警戒したり、悲観したりするほど大きいものなのだろうか。目立つには目立つけど、べつにアートの現場はフェアやオークションだけではないし、アーティストの活動も売買だけではない。あたかもマーケットがアート自体を危機に陥らせるような話は、僕には誇大妄想に聞こえるし、コマーシャルな活動が即セルアウト、というラディカルな論調も幼稚だと思う。
それに、金融経済的な作品の値段と、芸術的価値は必ずしも一致しない。いまも値段に相当しない芸術的価値を持つパフォーマンスとか、無形であるがゆえに市場と縁の薄い作品の価値は、値段とは別にキュレトリアルな場や大衆のなかで価値を高めている。逆に、新自由主義が世の一部である限りは、ダミアン・ハーストによるマーケットへのアプローチしかり、市場をレペゼン/ネタにするアーティストもいるだろう。そうした全体の絡み合いがあるなかで、ことさら一部に集中する批判は、それが壮大であるほどに、これはアートの本質を舐めているというか、むしろマーケットへの過大評価なのではと思うのだ。
ここに資本主義を「ウィズ化」できずに、大きく見積りすぎるというアクティビストの残念さがあるのだけど、とはいえ個人的な見解としても、アートマーケットにバブルの面はまだある。ただ、これが永遠であるとはさらさら考えていない。アートの投機性が加速したのは1990年代からで、新自由主義の影響下、つまりたった20年ほどの現象なのである。
新自由主義は、中流階級に富を分配することで人々の購買意欲を高め、生産と消費につなげるというフォーディズムへのカウンターだと言われている。フォードや、日本であればトヨタが代表するこの生産体制は、高度経済成長期の要請に答えるものとして、一般的な経済体制にもなった。しかし、そのあとフォーディズムが剰余価値を生み出す限界を迎えたときに、今度は富を自由競争の荒波に再分配しようと新自由主義が待望された。パラダイムシフトが起きたということは、またパラダイムシフトは起きるということだ。新自由主義という制度が、いまよりも自明視されなくなる時代は必ず来る。
その徐々に訪れるだろう時代において、市場原理主義的なアートマーケットはどう評価されるのか。想像するとゾッとするような作品もいくつか思いつく。それまでのパラダイムに隷属していたものを買い支える人はいなくなるわけだから、ある種のアートは暴落からまぬがれないだろう。とくにコレクターの動機が投機目的強めであった場合、作品の所有権は即行放棄される。しかしそれによって、我々の価値観もやはり変わらざるを得ない。アートの需要のされ方が変わるのである。
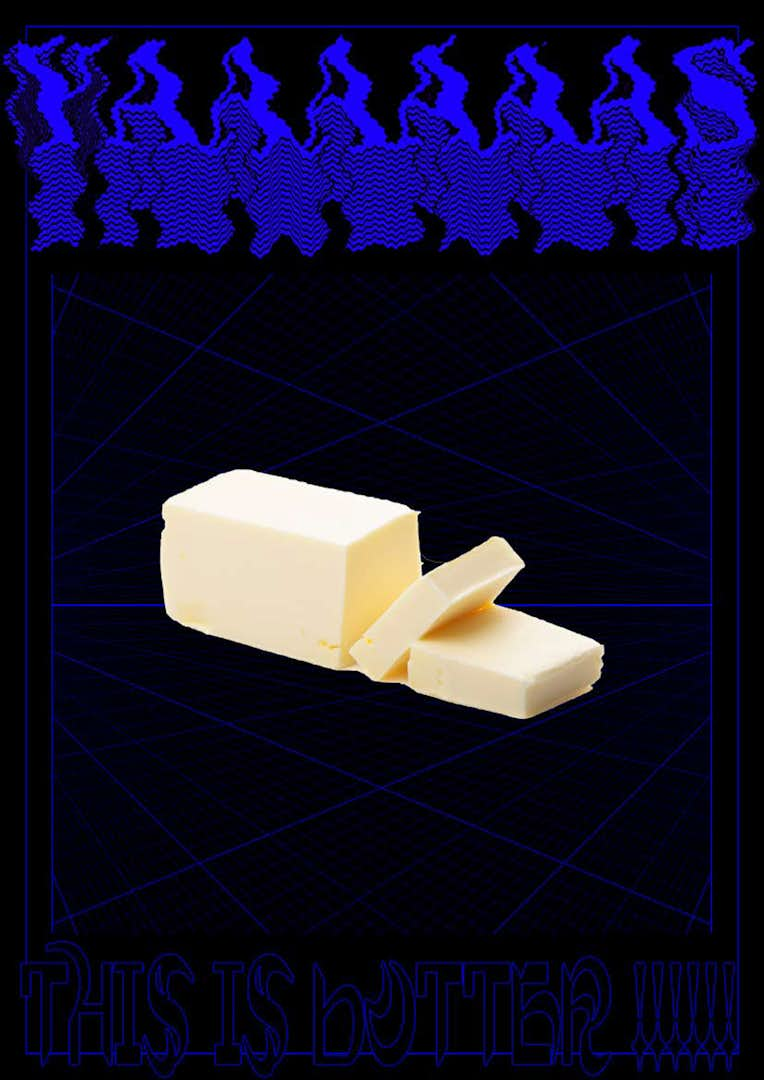
マーケット、美術館、大衆
かつて、アート作品の価値をコレクションとして担保していたのは美術館だった。いまも美術館は権威だけと、そのプレゼンスが下がった背景には、コマーシャルギャラリーと個人コレクターの勃興がある。
マーケットによる美術館の権威の相対化、美術村の脱構築は、アートシーンに新興プレイヤーの増加をもたらした。アカデミズムと無縁にアートを知り、ミヅマアートギャラリーのボランティアから始め、無人島プロダクションでChim↑Pomとしてデビューした自分にも、それは何パーセントか当てはまる。一方で、重要な作品の値段は高騰し、美術館は自らの体力では充分なコレクションができなくなった。いまそれを補填しているのは、個人コレクターによる美術館への寄付である。
美術館とマーケットは二極化しつつも、相補の関係を築いているだろう。互いの境界が曖昧になるにつれ、例えば売買の場であるメガギャラリーは公益性を打ち出して美術館化し、公立美術館には逆にビジネスが求められるようになった。アートの外の世界で言えば、ソーシャルビジネスの台頭と公共福祉のビジネス化という、経済と福祉の溶解もそれに近い。
僕の感じるところでは、マーケットと美術館のパワーバランスは、第三項である「大衆」の登場によってまた大きく変わろうとしている。現在、インターンやボランティアとしてブルシット・ジョブ(くそつまらない労働)を担当させられることも多い彼ら彼女らだが、SNSや芸術祭、参加型アートを中心にその当事者意識は増してきている。その本気が発揮されるのはきっとこれからである。また、DOMMUNE、にんげんレストラン、チームラボ、ストリートアート......サブカルチャー的に、ある種の支援とつながる入場料や、人気、フォロワーなど大衆の支持やサポートを活動源にしたネオ・ポピュリズムとも言えそうな作家のやり口は、既存の制度とは独自の距離を持つ。
大衆のモンスター化をアートに招いたあいトリで、公金とアートの議論がシリアスになったいま、コレクターと大衆のサポートはより公的な意義に向けて溶けだすことが期待されている。マーケット、美術館(ある意味芸術祭も)、大衆、その三者の力関係がウニョウニョとアメーバ上に溶け合った先には、きっとまだ見ぬバリエーションが産みだされるだろう。そして、1パーセントの富裕層の力が揺らぐときには、大衆は現在の「ファン」心理とはまた違う当事者意識を持った、「プレイヤー」へとその役割を高めるはずだ(そのときには「大衆」という呼び名も変わるかもしれない。何か「不特定多数の専門外者」のような意味を持って)。
そこで課題になってくるのは、大衆のエンライトメント(啓蒙)である。儚い希望だと知りつつも、労働者やフォロワーの意識は時代によって変わる。その可能性が一般社会に現れてくるのは階級闘争や市民運動だろうが、その真の意味での民主化とアートが連動できるかは、いまもソーシャリー・エンゲイジド・アートなど、大衆との関係性を高めるアートのミッションだろう。何にせよ、従来のやり方ではない大衆プレイによるイベントの仕組みや、ファンドレイジングの多様化はすぐに発明されるはずだ。また、ワークシェアリングや十分なベーシックインカムなどが進むとしたら、その余暇には「やりがい搾取」とはまた違う、例えば「市民が主体となる制作」のようなモチベーションのボランテティアワークも進むだろう。
美術館、マーケット、大衆......。いま、綿密に繋がりあってシーンを支える三者は、しかし同時に、現状のままではもうとっくに限界が見えているのも事実である。フォロワーのパイが大きくなればなるほどに、インフルエンサーの社会的価値は上がるだろうが、その反面、発言や表現はマスに向かって薄まっていく。大衆が消費者である現在、マスに向けたイベントや発言が増えるなかで、いかにアートは芸術的価値を追求し得るかが試されている。しかし、社会的価値ともども付加価値であるこの芸術的価値はむしろ反対に、その威力を孤独にこそ発揮する。
時空や体制によらない、芸術的価値
そもそも、アートが高額であるマトモな理由があるとしたら、そこには最低限、人類の財産という歴史の裏打ちがなければ嘘になる。この看板というか信用をおろすことは、マーケット側からしたってできることではない。そうなれば、それはもう、取引されるものがただの商品になってしまい、自らの価値を下げるだけだからだ。つまり、作品の価値は「商品価値」として計算できるような、シンプルに資本主義的なものではない。
「価値主義」とは、お金以外にも情報やフォロワーなど価値が多様化し、これまで最強だったお金が、新たな価値にとって変わられて、そのプレゼンスを下げることだという。資本主義社会以前に最強だった価値は、「身分」である。身分が高ければ金がなくても多くの物を手にできたように、情報化社会のいまは、貯金がゼロでもフォロワーや情報が多ければ、人材やお金、知恵をゲットすることができる。
このような交換の最大のチャンネルがアートにとって何かと言えば、言わずもかな「芸術的価値」だ。それさえあれば、何もなくとも、昔からアーティストは、パトロンからアトリエを提供してもらい、作品をお金に替え、生きる糧やコミュニティを得られ、何よりも発表の場という社会や時代を変える機会をゲットしてきた。
その原則に則って、アートは昔から、そもそもからして一般社会のセオリーから少し脱却しながら(独立性を持ちながら)存続してきた。社会の土台である経済体制は資本主義であったり、奴隷制だったり、封建制度であったり、政治体制は民主主義であったり、一党独裁であったり、いろいろだが、それぞれの時代と場所、それぞれの制度のなかで、ゆうに数百年の歴史をサバイブしてきた芸術的価値には、そもそも資本主義という一つの制度に縛られず、それを乗り越える力がプログラムされている(マルクス風に言えば、アートは経済という社会の土台である下部構造からも、上部構造の中では政治からも、独自の価値を築いてきた)。それさえあれば、資本主義であれその外であれ、社会の土台が何に変わろうと、価値の生産と交換は無限に行うことができるのだ......。
......なんて理想と性質からして、超超超公共的なものを所有するとなると、作品の売買自体もじつは単純に消費とは言い切れないものになる。例えば、美術館やコレクターが作品を買うことには、暗に、人類の共有財産を未来のために管理するという「仕事」が含まれている。まったく売らないという選択をするラディカルな作家もいる。しかし僕が敬愛する大正時代のアーティスト・望月桂がそうであるように、そうした作家の作品は遺族の倉庫に収まってしまう。望月がいまだにまともに評価を得ていない大きな理由のひとつは、研究者ですらその倉庫を開けるのが難しい、という遺族の理解度によるところが大きい。
マルクスは、貨幣の交換能力についてのメモで、貨幣は「あらゆるものを革命化する」と絶賛しつつ、オチとして、「愛は愛とだけ」、「芸術的教養を享受したいなら、芸術的教養を持った人間にならねばいけない」とその限界を定義しているが、まあ、資本主義を解剖してみても、結局のところ、愛やアートとはそんなものなのだろうと思う。
アーティストはいかなるシステムにも隷属せずに、遊び場にしたり、逸脱したり、乗っ取ったりすることに長けてきた。ここまでは現状や原則の確認をしてきたが、このあとはいくつかの例を追いながら、これからのことを考えてみたい。(Vol.2に続く)