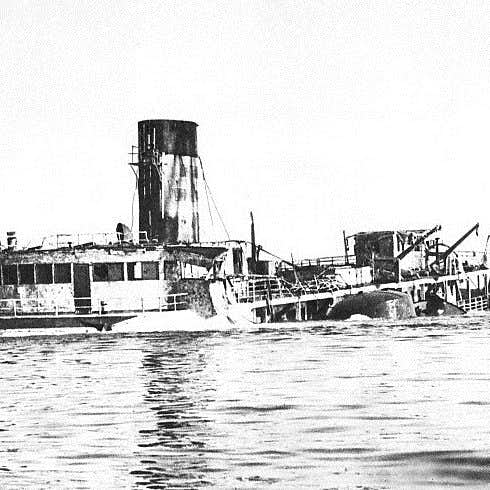黒瀬陽平が見た、
震災と高校生を描くF/T15『ブルーシート』
2013年、東日本大震災で崩落しブルーシートで覆われていた崖を臨む、高校のグラウンドで上演された演劇作品『ブルーシート』。飴屋法水が作・演出を務めた本作には、舞台となった福島県立いわき総合高校の生徒10人(当時)が出演し、話題を呼んだ。15年秋に開催された「フェスティバル/トーキョー 15」に際し、東京・豊島区の元中学校を会場として再演が実現。元生徒を含む高校生たちのやりとりを通して震災を描いたこの作品を、美術家・美術評論家の黒瀬陽平が語る。

「後」の時間の演劇 黒瀬陽平=評
1955年5月11日の午前6時56分、濃霧につつまれた瀬戸内海上で、宇高連絡船「紫雲丸」が貨物船と衝突し、沈没した。「国鉄戦後五大事故」のひとつに数えられる紫雲丸事故である。168名もの犠牲者を出したこの事故は世間に衝撃を与え、当時まだ構想段階だった「本州四国連絡橋計画」、つまり瀬戸大橋建設を推進するきっかけにもなった。
何よりも世間の人々の心を痛めたのは、沈没した紫雲丸に、修学旅行中だった小中学生が乗っていたということだ。事故によって犠牲になった修学旅行関係者は108名、うち100名は修学旅行を楽しむ児童たちだった。突然海に投げ出された児童たちのうち、泳ぎが苦手な子たちから犠牲になった。紫雲丸事故がきっかけとなって、全国の小中学校に水泳プールの設置が進められ、水泳の授業が採用されるようになったという。
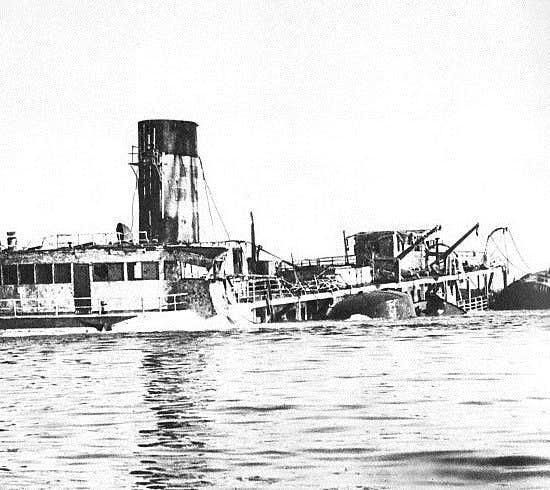
最近、ぼくはとあるプロジェクトを準備するなかで、紫雲丸事故について調べることになった。ぼくは高知生まれで、高校卒業まで高知で育った。だから、紫雲丸事故について深くは知らなかったものの、まったく縁がないというわけでもなかった。というのも、高知市内の中学高校の教諭であった母がかつて勤務していた高知市立南海中学校の3年生117名が、1955年5月11日の紫雲丸に乗船していただからだ。117名のうち、28名が帰らぬ人となった。
母に連絡し、南海中学校の校長先生にアポイントを取ってもらい、数名のアーティストとともに南海中学校を訪ねることにした。プロジェクトのリサーチで、実親に段取りをしてもらうというのも不思議な感覚だ。ちなみに父親は、宇高連絡船の中にあったうどん屋がとても美味しく、その店は大阪万博にも出店したのだ、という話をしていた(真偽は確認していない)。
校門のすぐそばに、紫雲丸事故の記念碑がある。この記念碑の前で追悼式典がおこなわれる様子を、地元のテレビニュースで見た記憶が蘇る。記念碑の近くに、なにやらミニチュアの潜水艦のようなものが置いてあった。こちらは見たことがない。近づいてよく見ると、「津波避難シェルター『救難まんぼう』」と書いてある。どうやら先の震災を受けて、津波避難学習の一環として導入したものらしい。6人乗りの小さな津波避難艇だ。海がすぐ近くにある南海中学校にとって、津波はもっともリアリティのある災害のひとつである。
校舎に入ると、ちょうど休み時間だったのか、生徒たちが勢いよく廊下を走っていった。ぼくたちは、教室のひとつを改装した「紫雲丸遭難事故学習資料展示室」という部屋に案内された。そこでは、紫雲丸事故についてのパネル展示や、遺族の方々からのメッセージ、生徒たちでつくったジオラマなどが展示されていた。それらひとつひとつが、事故の記憶の継承のかたちとして胸をうつものだった。

ある小さな記事の前で立ち止まった。「行くはずだった修学旅行」と題されたその記事は、事故から49年後の2004年5月11日に、事故から助かった南海中の同期生39名が、事故で中座してしまった修学旅行を、およそ半世紀ぶりに「やり直す」ために出発したことを伝えていた。しかも、同期生たちは亡くなったクラスメイトたちの遺影を持参し、バスに乗って京都へ向かったのだ。
記事には、49年前の見学予定地だった三十三間堂を見学する同期生たちの写真があった。もちろん両手には、クラスメイトの遺影が抱えられている。そこには、中学生のままのクラスメイトとともに京都見学をする、初老の「修学旅行生」たちの姿があった。

世界には、理不尽な事故や災害がある。生き残った当事者たちは、その「後」の時間(木村敏が「ポスト・フェストゥム」と呼んだような時間)を生きなければならない。その事故や災害を境に変わってしまったこと、取りかえしのつかないことを受けとめて、「後」の時間を生きてゆく。
紫雲丸事故のエピソードはぼくに、当事者にとっての「後」の時間について、そして「後」の時間のなかに訪れた、ひとつの区切りについて、考えさせるものだった。「後」の時間は、決して「前」の時間と同じにはならない。「渦中」をさかのぼって、もとどおりになることはない。
しかし、「前」の時間から失われてしまったものが、別のかたちをとって、「後」の時間に合流してくることは、きっとあるだろう。紫雲丸事故の生存者たちのように、「後」の時間を生きるひとたちが、失われてしまったものを記憶し、思い出しつづける限りにおいて。

2013年1月末に福島県立いわき総合高等学校で発表された『ブルーシート』の初演は、「渦中」の時間に属する演劇であったと言うべきだろう。震災の当事者である10人の高校生たちが、被災した自分たちの高校のグラウンドで、そのほとんどがアドリブではないかと思われるようなやりとりをする(実際は、台本の9割は飴屋法水による創作だという)。そこで話されること、身振り、手振り、すべてが、震災のメタファーとして現れてしまう。それがどんな些細で、たわいのない高校生のおしゃべりだったとしても、震災と無関係に見ることが不可能であるような状態。それこそが、「渦中」の時間である。
いっぽう、再演された『ブルーシート』は、まさに「後」の時間に属する演劇だった。かつて「渦中」の時間を演じた高校生たちは高校生ではなくなり、人によってはいわきからも移住し、そのうちのひとりは、家族をもったことによって出演することができなかった。いわきではなく、東京の廃校のグラウンドで、彼ら彼女らは、2013年と同じ演技を繰り返す。しかしそれは、「渦中」の時間はすでに過ぎ去ってしまったのだということ、ぼくたちは「後」の時間を生きるしかないのだ、ということを突きつけるのである。
ぼくは、その演出が不満だった。起こってしまったことは取り返しがつかず、過ぎ去った時間は戻らない。そんなことはとっくにわかっている。悲しいほどに、わからされている。「前」の時間と、「渦中」の時間と、「後」の時間、それらの差異、どうしようもないズレ、不可逆な時間を強調するだけの演出を、ぼくは受け入れることができなかった。

「後」の時間を生きるとは、失われてしまった「前」の時間や「渦中」の時間にあったことの、「何を忘れないか」を決めることであり、それを「どのように記憶し続けるか」「どのように思い出すのか」を考えることである。たしかに、再演された『ブルーシート』では、過去は反復され、記憶され、思い出されていたかもしれない。しかしその反復や想起は、彼ら彼女らが成長し、場所を変え、時間が経ったとしても、いつまでも、どこまでも追いかけてくる悪夢のような「渦中」の時間であるように見えた。
その悪夢を断ち切るためには、失われてしまったものが「いつか別のかたちで帰ってくるとしたらどのようなかたちがありうるか」、を想像するしかない。もちろん、その想像力を、まだ若すぎる彼ら彼女らに求めるのは無茶なことだ。紫雲丸事故の生存者たちでさえ、半世紀もかかったのである。
しかし、現在の彼ら彼女らの想像力に寄り添い、悪夢のように襲ってくる「渦中」の時間の反復のただなかで生きる姿しか描くことができないのであれば、それは悪い意味でドキュメンタリーに過ぎないのではないか。当事者ではない演出家だからこそ、当事者にはない想像力を重ねあわせることができるのではないか。
彼ら彼女らのもとにいつか、失われてしまったものが別のかたちで帰ってくるとしたら、どのようなかたちがありうるだろうか。もし、そのような想像力がないのなら、芸術が「後」の時間を扱う意味はない。