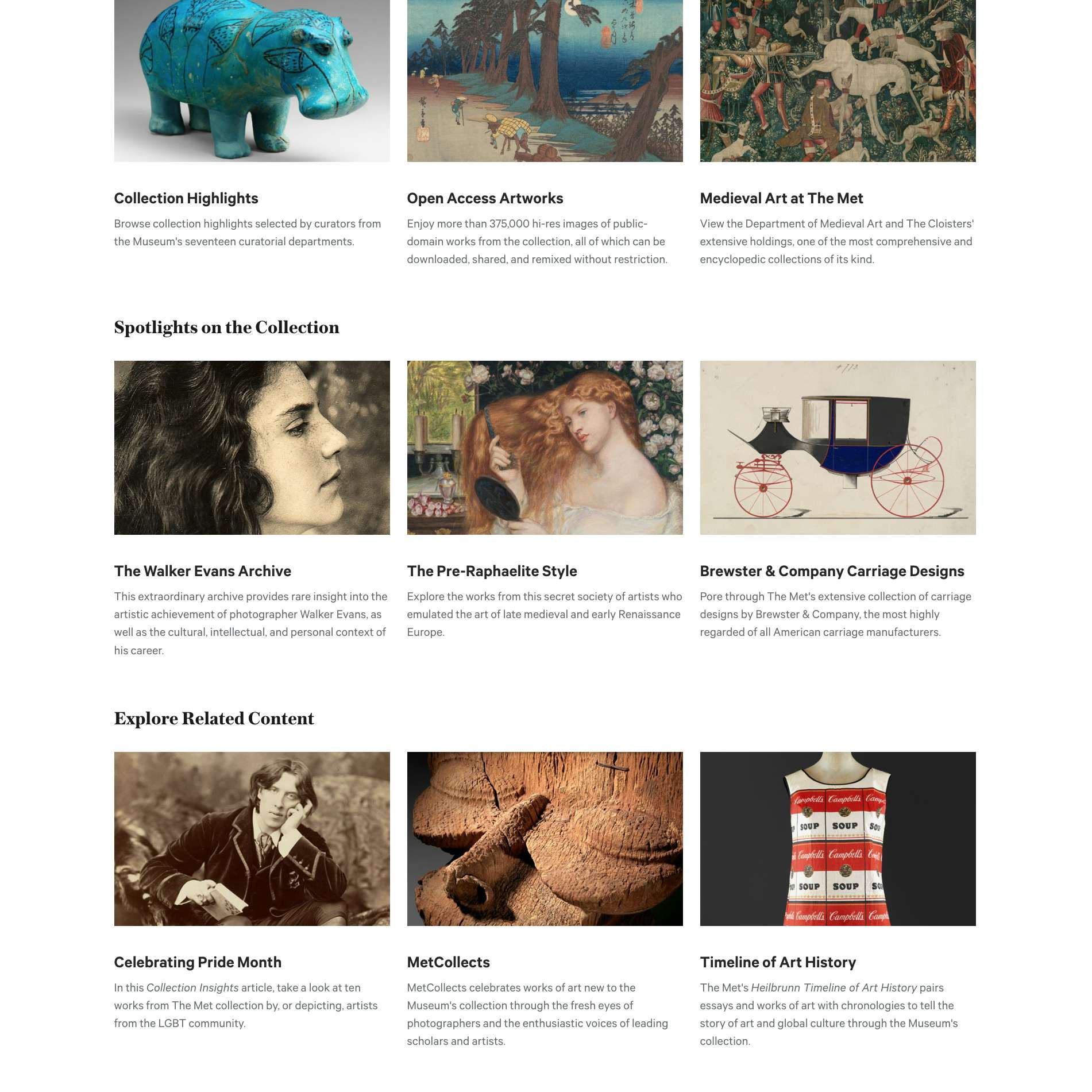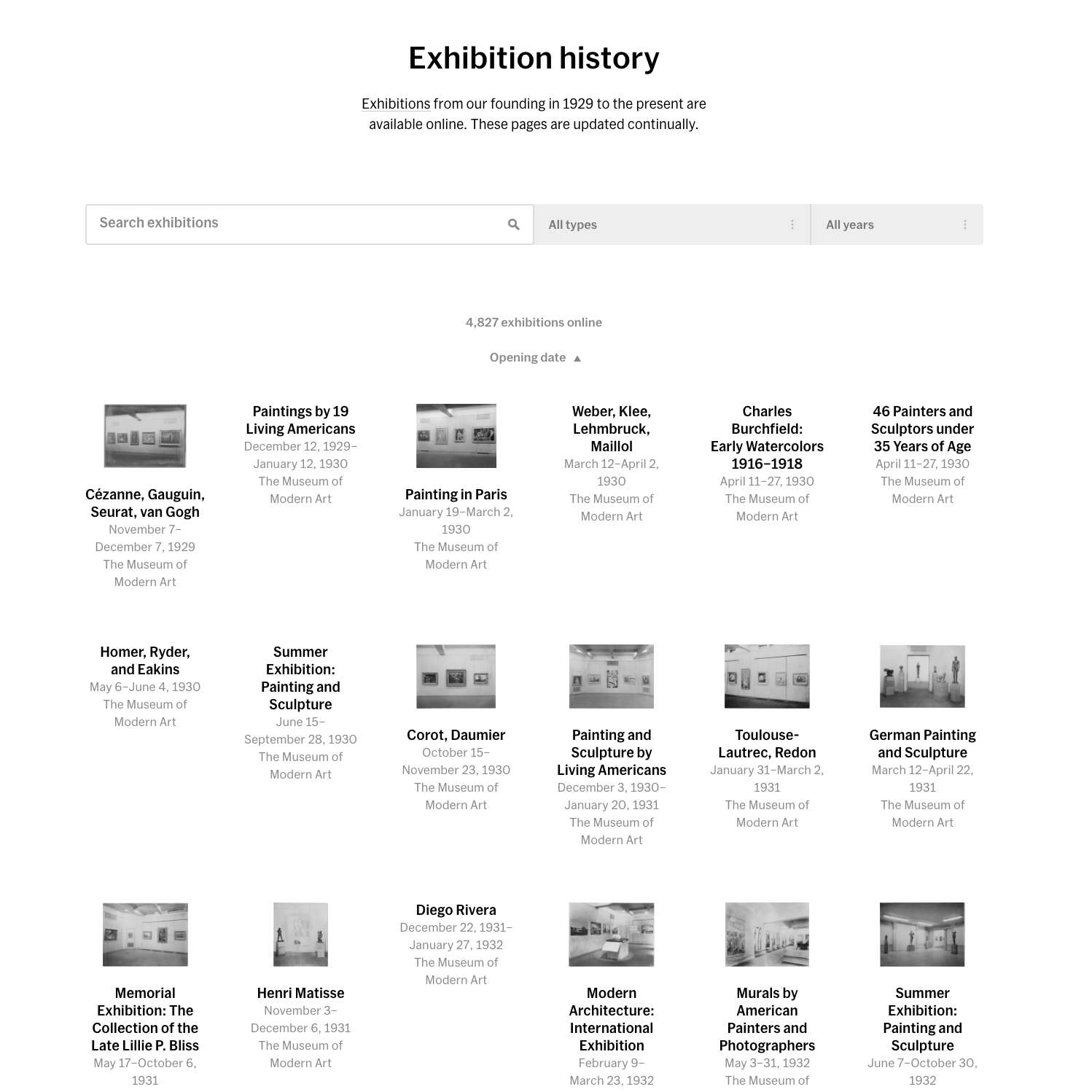シリーズ:これからの美術館を考える(1) 加治屋健司が提示する「共同研究の活性化」と「アーカイブ機能の強化」
5月下旬に政府案として報道された「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想を発端に、いま、美術館のあり方をめぐる議論が活発化している。そこで美術手帖では、「これからの日本の美術館はどうあるべきか?」をテーマに、様々な視点から美術館の可能性を探る。第1回は東京大学大学院総合文化研究科准教授・加治屋健司の論考。

大学の研究者として、そして、美術館の利用者として、私は、これからの日本の美術館は研究機能の充実を図るべきであると考えている。それは、展覧会やコレクションの価値を高め、美術館が本来の業務に集中することに貢献するだろう。日本の美術館には、他にも、学芸員以外の各種専門職員の雇用や指定管理者制度の見直し、展示面積の拡大など、取り組むべき課題はあるが、今回はこの問題に限定して述べることにしたい。
なお、筆者の専門は現代美術史なので、主に現代美術を扱う美術館を想定して意見や期待を述べている。筆者は学芸員ではないため、なかには的外れなものもあるかもしれないが、美術館から離れているからこそ見えるものもあるに違いない。美術館を取り巻く環境を考えるための一助となれば幸いである(美術館学芸員が考える美術館のあり方については、昨年5月に全国美術館会議が策定した「美術館の原則と美術館関係者の行動指針」を参照するとよい)。
共同研究の活性化
国立美術館には、すでに科学研究費を用いて展覧会やコレクションに関連する共同研究を行っているところもあるが、大学教員や他美術館の学芸員などが参加する共同研究の数は少ない。展覧会で扱う作家や動向に関する議論を広げていくためには、展覧会やその関連イベントだけでなく、多様な研究者が参加する、展覧会やコレクションに関する共同研究や研究会を開催することが重要である。研究を波に例えるならば、波は突然始まったり終わったりするものではなく、その前にも後にも小さな波があって、だからこそ研究は持続し拡散し「波及」していく。研究書の場合、刊行前の口頭発表や学術論文の段階で様々なフィードバックがあり、刊行後も書評会が開かれたり、場合によっては反論が登場したりして議論が続いていく。展覧会を到達点とする調査研究もまた、波状化・クラスタ(房状)化することで、その研究成果をさらに持続させ拡散させていくことができるのではないだろうか。
コレクションの形成といった中長期的な取り組みに関しても、多様な研究者が参加する共同研究や研究会は有効である。ニューヨーク近代美術館が行っているC-MAPは、同館が精通していないアジア、中欧・東欧、ラテンアメリカに関する調査研究を行うものであり、テートの「リサーチ・センター:アジア」もまた同様の試みである。もし、美術館がこれから展開したいと考える分野があれば、その分野の大学教員や大学院生とともに研究会を行うことで、その分野の知識を増やすことができるし、参加する大学教員や大学院生にとっても、異なる環境によって研究上の示唆を得られるというメリットがある。
つまり、美術館と大学の人事交流はもっと進むべきなのである。いままでは、キャリアを積んだ学芸員が大学に移ったり、あるいは大学教授が館長になることが多かった。これから必要なのは、上記のような共同研究や研究会など、双方に研究上のメリットがあるような交流ではないだろうか。そのためには、昨年7月に日本学術会議が提言「21世紀の博物館・美術館のあるべき姿―博物館法の改正へ向けて」で指摘したように、今よりも多くの学芸員が科学研究費代表申請資格を得ることができると共同研究がしやすくなるだろう。大学も、学芸員の希望に応じて客員教授・特任教授等として受け入れ、調査研究がしやすい環境を提供できるとよいだろう。また、他方で、米国の一部の美術館にあるように、美術館が大学教員をシニア・フェローとして一定期間受け入れて、美術館のコレクションや資料を活用した研究に従事してもらうことも、それらの価値を高める点で大きな意味がある。
アーカイブ機能の強化
いくつかの美術館は、図書室がアーカイブ資料を受け入れるなど、すでにアーカイブ機能の強化に取り組んでいるが、その数は少ない。フォーマリズムだけでは研究が成り立たなくなった今日、作品が制作・流通・受容された文脈に関する情報は不可欠となっている。そうした研究動向を後押しするかのように、アーカイブ資料やオーラル・ヒストリーを収集している国は少なくない。しかし、日本にはそれらを主要業務として収集している公的機関は存在しない。近年でも、ヨシダ・ヨシエの資料の一部が、国内では引き取り手がいなかったために、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の図書館に収められたことは記憶に新しい。次の点にも関連するが、美術家等が所有している写真、ノート、草稿、手紙、新聞雑誌の切り抜き等を参照したり、美術家本人から話を聞いたりすることは、現代美術の研究では不可欠であるが、日本では彼(女)らと個人的な関係を構築しないとできない場合が少なくなく、若手研究者や海外研究者の参入を困難にしている。こうした美術資料を収集して、研究環境を整備することができるのは、やはり美術家等との関係を構築している美術館しかないだろう。
資料へのアクセスの改善
日本の美術館は、海外の美術館に比べると、ウェブサイトを十分に活用していないように思われる。日本の美術館のウェブサイトは、もっぱら、美術館を利用するのに必要な情報があるだけで、ニューヨーク近代美術館やテートのように(*1)、展覧会やコレクション、それらに関連する美術史・美術用語について学ぶ場にはなっていない。作品の写真がある場合でも、あまりに小さくて役に立たないものが多い。メトロポリタン美術館は、37万5000点の所蔵作品の高画質の画像を公開している。ある程度の画質の画像があれば、そこから議論が可能になるため、コレクションに関する研究を増加させることになるし、長期的にはその価値を高めることに貢献する。
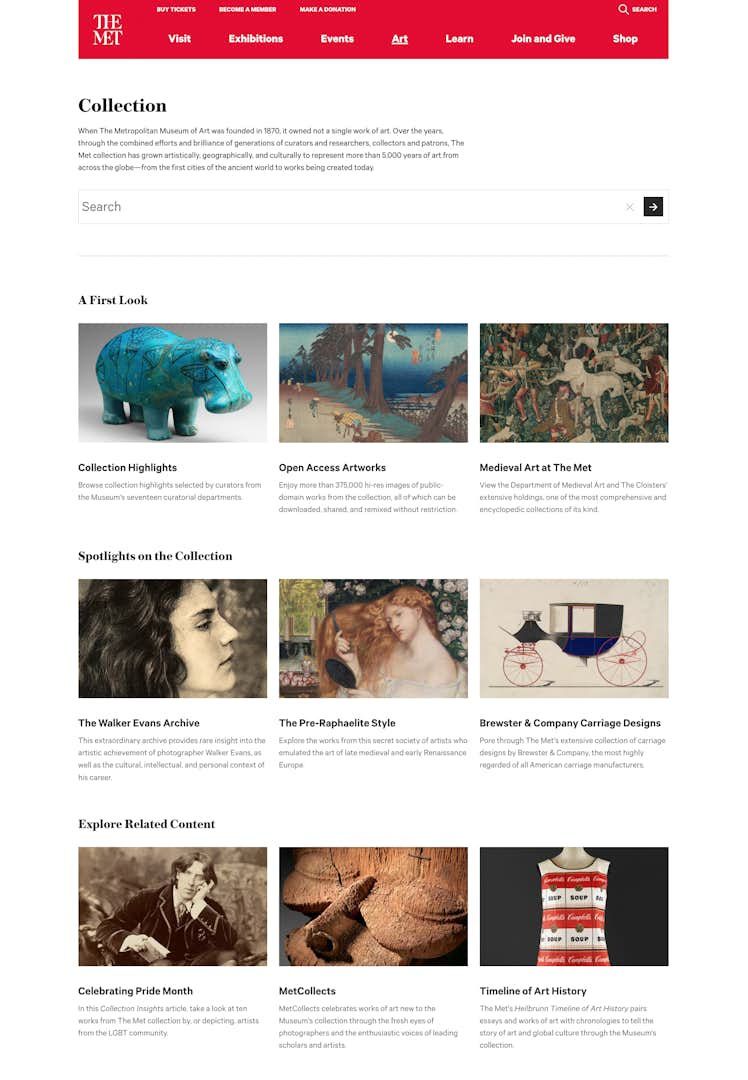
近年、米国の美術館を中心に、展覧会の写真や資料の公開が進んでいる。ニューヨーク近代美術館は、過去の展覧会の展覧会カタログ、報道資料、会場写真を公開しており、グッゲンハイム美術館も、200冊以上の展覧会のカタログを公開している。Afterall Booksの「展覧会の歴史」シリーズの研究書が示しているように、展覧会の写真はかなり多くのことを教えてくれる。日本でも、「人間と物質」展(1970)の会場写真を見ると、参加作家のサイトスペシフィックな取組がよくわかる。展覧会に関する資料の公開は、展覧会研究だけでなく、作家や作品に関する研究にも大いに役立つのである。
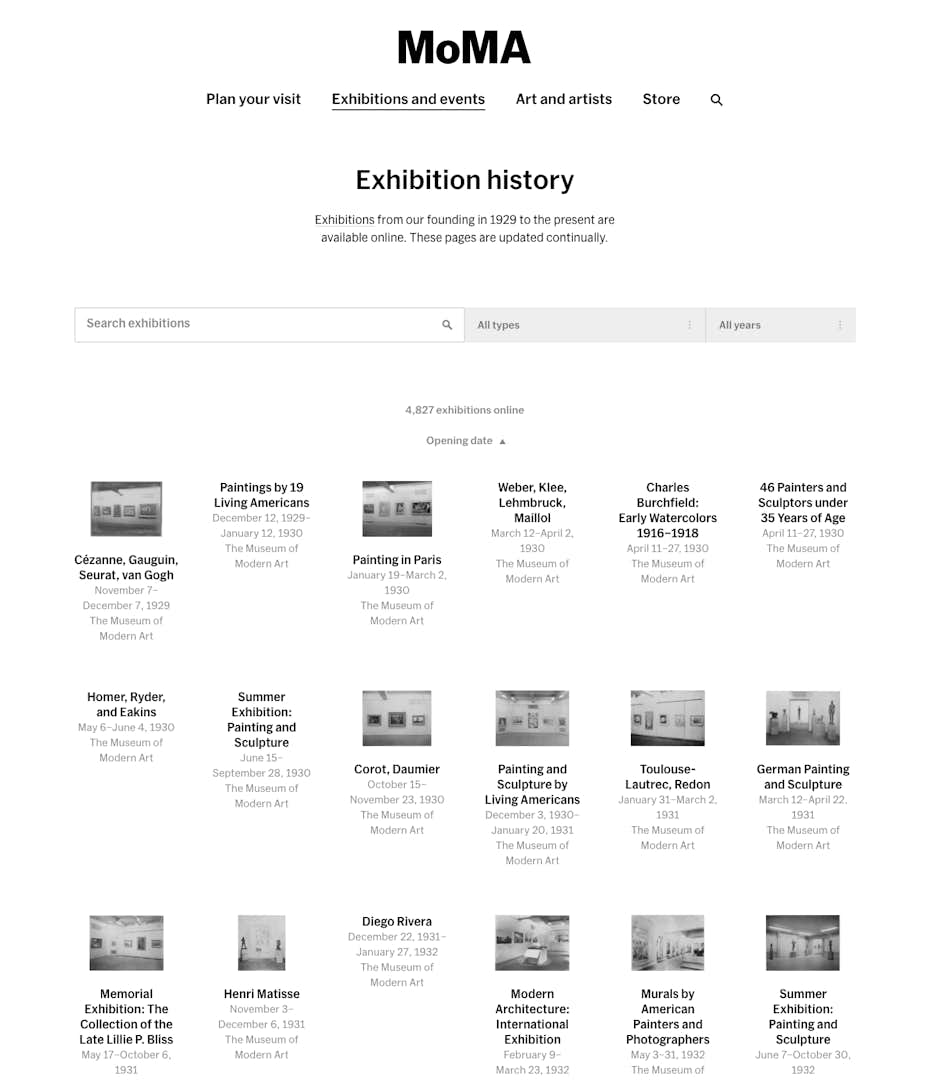
資料へのアクセスという点では、展覧会カタログが流通しにくい状況も改善の余地がある。日本の美術館の展覧会カタログを海外の研究者が購入するのは極めて困難である。日本の美術館の大半は、現金書留でないとカタログが買えない(国内研究者にとっても、毎回郵便局に行く必要があるため、時間のロスである)。美術館のウェブサイトでオンライン決済できるようにするなど、なんらかの仕組みをつくる必要があるだろう。
今年3月に閣議決定された文化芸術推進基本計画(第1期)で示された数多くの施策の中には、日本の美術を海外に向けて広く紹介するために、海外で展覧会を開催したり、学芸員のネットワークを構築するというものがあった。美術館のウェブサイトで、作品や展覧会の写真を見ることができたり、戦後日本美術を学ぶことができたり、展覧会カタログをオンラインで購入できるようになれば、海外での展覧会の効果を持続させ増幅させることができるのではないだろうか(ただし、日本の展覧会カタログの英訳の質は上げなければならない。出版可能なレベルの英語になっていないものが多いため、エディターによる校正・編集を導入するべきである。英文のエディターは日本語ができる必要はないため、翻訳者よりも探すのは容易であるように思われる)。
地方美術館の研究環境の整備
現在、図書室を一般公開している美術館は首都圏に集中しており、関西では、京都国立近代美術館も国立国際美術館も図書室を一般公開していない。一般の公立図書館には美術書や美術雑誌が少なく、とくに海外の文献がほとんどないことを考えれば、地方都市こそ、美術館図書室へのアクセスが求められている。そして、地方で活動する作家の資料やオーラル・ヒストリーの収集は、知識も人脈もある地方の美術館が率先して担うのがよいように思われる。地方で行われる芸術祭の資料も同様である。芸術祭が開催されなくなると事務局が解散して資料が散逸してしまう可能性が高い。そうした資料を収集・保管できるのは地元の美術館しかないだろう。先日の「リーディング・ミュージアム」の構想を見ると、これから国公立美術館の役割の明確化が進み、地方美術館は主に地域社会への貢献を求められることが予想される。しかし、地域にコミットすることは、その地域での価値に加えて、歴史的な価値を持った重要な活動であるということは、いくら強調してもしすぎることはないだろう。
以上、簡単ではあるが、研究機能の充実の観点から、これからの日本の美術館はどうあるべきかについて考察してきた。具体的な取組としては、共同研究の活性化、アーカイヴ機能の強化、資料へのアクセスの改善、地方美術館の研究環境の整備の4つを挙げた。一見すると、これらは大学研究者にとってメリットがあるものにすぎないように見えるが、いずれも、美術館の展覧会やコレクションの価値を高め、美術館の存在意義をより確かなものにするだろう。
昨年6月に制定された文化芸術基本法は、第29条の2で「調査研究等」という項目を新設している。本稿で述べた美術館の研究機能の充実は、この「調査研究等」とは直接は関係していない。第29条の2の「調査研究等」とは、文化芸術を、その振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野で用いるために行われるものを主に想定している(*2)。美術館が近い将来、こうした各関連分野への展開を求められたとしても、美術館の研究機能の充実は、その本来業務の重要性を高め、学芸員が業務に集中する環境を強化することに貢献するだろう。
脚注
*1——https://www.moma.org/learn/moma_learning http://www.tate.org.uk/art
*2——河村建夫・伊藤信太郎編『文化芸術基本法の成立と文化政策―真の文化芸術立国に向けて』(水曜社、2018年)、114頁.