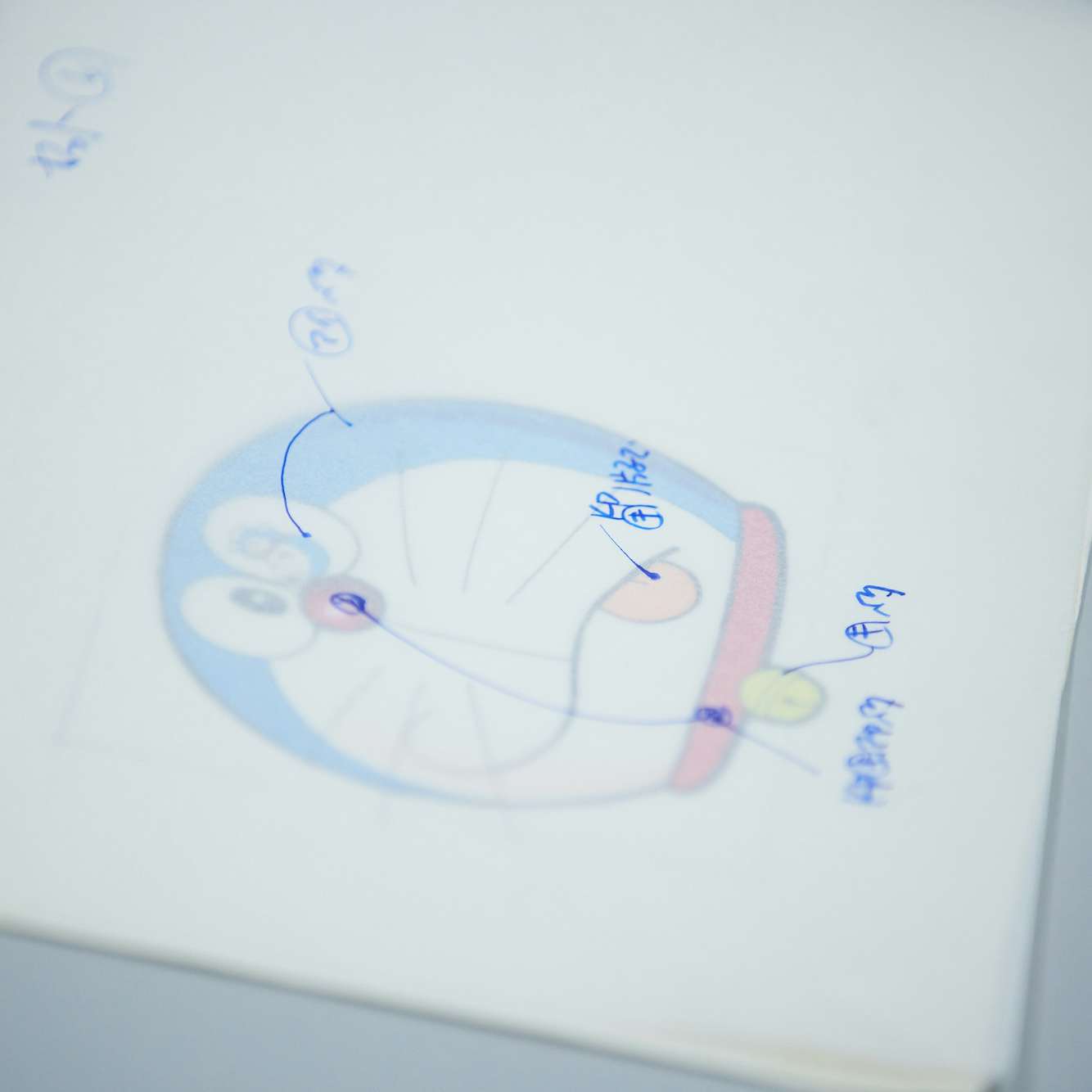山口晃が向き合う『ドラえもん』の原画たち。「これぞ名人芸」
50周年を迎えたマンガ『ドラえもん』。その原画を拡大することで「絵」として『ドラえもん』を鑑賞するという書籍『THE GENGA ART OF DORAEMONドラえもん拡大原画美術館』が発売中だ。これを機に、「THE ドラえもん展」にも参加した経験を持つアーティスト・山口晃が『ドラえもん』の原画と向き合った。

マンガの原画を絵として鑑賞するコツとは?
1970年生まれの『ドラえもん』と1969年生まれの山口晃。「ガリバートンネル」や「インスタントミニチュア製造カメラ」などのひみつ道具を愛していた画家が、『THE GENGA ART OF DORAEMONドラえもん拡大原画美術館』に収められた直筆原画をじっくり鑑賞。“マンガを読む”とは別種の“原画を観る”ことの楽しみについて語った。
『THE GENGA ART OF DORAEMONドラえもん拡大原画美術館』に収められたもののうち、山口が実物を見たい!と挙げたのは、カラー絵、2色刷り、モノクロページが入り混じる30点の原画。「発表された年代と、コマやカットの性格というのでしょうか、それぞれが違ったものをお願いしました」。取材がスタートすると、静かな部屋に「いやあ……おお、ほお。へええ。ひょお……」という呟きが響く。

その意味するところを尋ねれば、「カラーの塗りを観たいと思っていたんですが、むしろ墨がパーンと目に入ってくるんですね。色がのることで黒い線が綺麗にみえる」との答え。カラー絵の、まずは線を凝視し、続いて色を堪能。そして視線は再び線に戻る。
「ガッシュまではいかないけど思ったよりも粒子がしっかりしているし、半透明水彩でこんなに濃く、よくまあこんなに平滑に。Gペンなのかと見まごうほどのカブラペンの野太さもいいですね。ひっかける感じでツッと入ったところにグッと力をのせザッザッと気持ちよく決める。形と呼応しながら自然な抑揚がついて、この頃ならエフェクトとして貼り付けられるような風合いが生でおこってるんですもの。いやあこれぞ名人芸ですね」。
マンガの原画を絵として鑑賞するコツのようなものはあるのかと山口に聞いてみた。
「マンガにはコマがあって、コマが割られセリフがふられると、絵の時間からマンガの時間へと変わり、ひとつの絵にとどまっていたくても、次のコマ、次のページへ押し流されて、読み手は絵の中を逍遥、回遊することが許されなくなる。ですからこの画集のようにコマを抜き出してあげたり、吹き出しを途中で切ったりすることで、読むことから解放され観ることにシフトしやすくなると思います。写植が剥がれていればさらにいい。絵巻における詞書のような感じでしょうか、茫洋とした空間のなかに言葉が原子的に分解されて消えていくような……不可思議な物理法則が働いているようにも思えます。なんの目的で描かれたなんなのかという情報は最初に外してしまって、コマの内と外、原稿用紙の内と外の区別をなくすと、紙の余白や原稿が置かれた机など、背景化されていたもののヒエラルキーもなくなっていく。枠外に書かれた文字や鋲の穴の痕跡もいいですね。恣意的にすべてを調節できるマンガの画面から、違う位相、異なる意識レベルのものを入れこんでみるわけです」。

マンガを読む作法を体得してしまった身には、読むことからの解放はいささか難しいことのように思える。ましてや相手は『ドラえもん』。油断すると声さえ聴こえてきかねない。
「例えば絵を逆さまにしてみると文字が読みにくくなりますよね。絵が壁にかかった状態ではなく、今日のように平置きしたものを上から眺めるというのもいい影響を与えそうです。鑑賞者が下を向くことで三半規管の働きがすこーし弱くなり、パースをとりにくくなることによって描かれているものがグッとせり出してくる。それによって、隙間の形や描かれている物のつながりまで観えてきます」と、『ネコが会社を作ったよ』の見開きを覗きこむ。

「ひゃあ、これは、これは。剥がれたテープの跡が綺麗ですね。いいですね、デカルコマニーみたいになっている。ホワイトの散らばりも効いています。これが塗られることで、背景だった余白が図と同じレベルまでせり出して、逆に図には穴があいて存在していたレイヤーが一枚消え、画面の空間性が変化しています。原稿用紙に引かれているレディメイドの線、事後的にひかれた線、意図して描かれた線、それぞれによって様々なリズムが生じているところに、編集さんだろうか、誰かが手書きした数字と『四年生』『コロコロコミック』の判子。違うタイプの時間が封入されていくつもの層ができていますよね。このホワイトの美しさ! 中西夏之さんの作品の気持ち良さを思い出させます。のび太くんの、こののどけき表情がまたいいですね。3コマ目の首からのたちあがりのこの角度、難しいんですよ」。
ドラえもんを丸で描くとまるで似ない
「ドラえもんの造形って初期は丸いんですが、ある時期から頭は少し前が膨らんで後頭部が削れて、重心はやや上に、鼻を頂点にして顎がちょっとひくんです。体のふくらみも内圧と外圧が絶妙に均衡した微妙なラインで描かれる。いくつかの原理が交錯する、関節の着脱も自在な世界。のび太くんにしても、3次元的に造形するとありえないってところに手がボコッと置いてあったりするんです。腕や脚が太くて短いので、関節を動かすことを想定すると造形ができない。浄瑠璃人形と一緒で、体の先っぽから決めていくとその間って勝手につながってみえるんですね。脚の膨らみ、体の線にもそうばかに長い線はなく、キュッ、キュッ、シュッと、藤子F先生のパーツで気持ちよく収まる形が連続している。これってなんでしょう、藤子F先生がカブラペンを使うときの曲線に適応したのかしらん。横滑りするカブラペンの線を従わせようとするんじゃなく、それに沿って出てきた形に自然と収まっていっているように見えて、“藤子カーブ”なんて呼びたくなるほどです」。
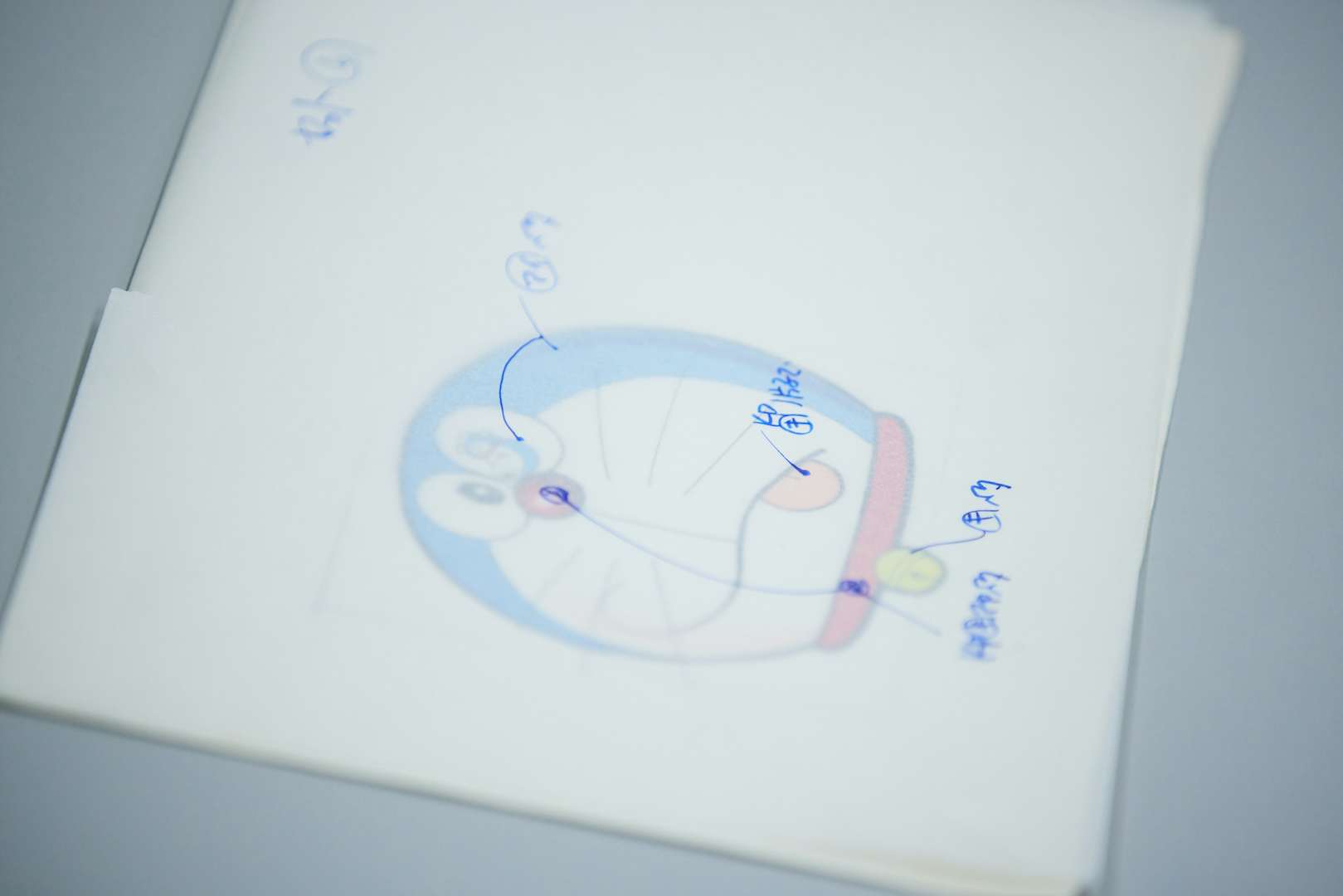
「『THE GENGA ART OF DORAEMON ドラえもん拡大原画美術館』の浦沢直樹先生とむぎわらしんたろう先生の対談に、藤子F先生は線をひくのが遅かったと書かれていましたが、ディック・ブルーナもそうなんですよ。ミッフィーちゃんの輪郭をチコチコチコ、と描いていく。線をビュッとひいてしまったら、ましてやロットリングでキューとか、自由曲線なんかで描いた日には!絶妙のおぼつかなさからくる愛らしさがでない。ちょっと描いては立ち止まり、見極め、少しずつ、少しずつ描く。鑑賞者の目には、そういった揺らぎが含まれた味わいのようなものも映るんですよね。そういった揺らぎはマンガ雑誌の紙でこそ拾いにくいけれど、今度は紙の粗さが奏功して、その紙だからこそ出る風合いにメディア変換される。単行本になるとまた紙が変わりますが、線のニュアンスがもう少し拾われるので縮小が可能になるんですね。紙の違いが与えてくる印象の違いというのはそれほどまでに大きくて、そこに優劣をつけることは可能なんでしょうけども、違いとして並列させて観るほうが楽しいと思うんです」。

2017年に始まり、いまも全国を巡回中の「THE ドラえもん展」への出展作品「ノー・アイテム・デー」で、山口もまたドラえもんとのび太を描いている。
「僕が描くとね、ドラえもんの頭の形がとれないし、お尻の肉もあまってしまう。背骨のラインも違っているし、どうしても関節を描いてしまうんです。子供の頃から絵描き歌で何度も描いたキャラクターなのになにしろ難しい。のび太くんも3頭身以下にするとバランスがとれなくて、眼鏡にも苦労しました。この眼鏡、ある瞬間には顔から浮き、別の瞬間には貼り付いていて、じゃあ何度傾くとそうなるの?と考えても規則性がわからない。上唇のかえりは人中をしっかり描いたときの残りのラインでしょうか。角度や口の開き方によって出る時と出ないときがあるんですよね。関節もそうですが、藤子F先生が描かれる最適なラインは3次元的整合性から少し離れたところにあって、とにかく難しい。『のろいのカメラ』ののび太くんの顎の外れかた、観てください。『新オバケのQ太郎』の『サンタはくろうする』で、Qちゃんが『アジャラカピー』と叫ぶコマを思い出させるこんな顔、この表情、いったいどうしたら思いつくんだろう!?」と、おもむろにペンを取り、ホワイトボードに絵を描き出す。

「目はこれだとまだ足りない」と絵を観に戻り、「ああ意外に正面気味なのか。顎は割と薄い。なるほどこうすると口を開いてる感じがしますね。うーん。僕が描くとどうも邪気が出てしまう、何かを捨てきれていないんでしょうか(笑)」と修正を加えながら線を探していく。「でもこうして描いてみると、形が形を呼んでくる。のどちんこ描いてみようかな、目を血走らせてみようかな、と描きながら、ああこうなったか、じゃあこうしてみよう、と絵が呼び起こされていくんですね」。
動く?動かない? カラリと乾いた子供の絵
「藤子F先生の絵に流れている時間ってなんだろう? と不思議に思うんです。止まっているようで動いている、動いているようで動きすぎていない。西洋の絵画が活人画的といいましょうか、わりに止まっているのに対して、日本の絵ってもうちょっと観念的なところからきていて、走ってる絵だったら走っているんです。藤子F先生はその中間というんでしょうか、止まっているけど動いてもいて、なんと言えばいいのかな。これは藤子F先生の絵と線のカラリとした乾き方、人間臭さが極限まで抜き取られているというところに通じていく話でもあると思います。テレビで『笑点』の楽屋が映されると、出演者たちが普段着でタバコを吸っていたりするでしょう? 例えばそういう、子供の心を波立たせてしまうかもしれない“大人っぽさ”というものを、絵では見せないと意識してらっしゃったんじゃないだろうか。子供さんを前にしたときはいい人になるんだ!と決められていたかどうかはわかりませんが、そういうところに起因して、形が走ったり流れたりせず固さを持つようになっていき、藤子F先生の個性に忠実に空間が構成されていく。それは恣意的ななにかというよりは、藤子F先生がメディアや形態というものにご自身を沿わせていったために、表層的なこだわりのようなものが消えていき、それ以上は拭い去れない、生理とでもいうべきものが表出することでこういう曲線に至ったのではないか、と思えるんです」。

『オバケのQ太郎』の絵とは連続しているようで違っている、『ドラえもん』という作品を描くうちに確立されていったであろう“流れなさ”。そこに読者への意識を読み取った山口は、藤子・F・不二雄の絵に「子供」の姿を見ている。
「『オーケーマイク』のこのコマ見てください、子供の絵みたいなんですよ。子供って、紙の特等席に一番描きたいものを描いたら、次どこにしよう?といい場所を探してまた描きたいものを重ねずに描く。モチーフを描くたびごとに一番いい場所を選ぶから、不思議と構図が決まるんです。紙の端への意識も鋭敏です。でも成長するに従って視認性が上がり、物が名づけられ観念化してしまうと、紙との関係で物を観ることができなくなってしまうんですね。一度それができなくなった人間が訓練でそれを取り戻していった絵とでもいうんでしょうか、このコマは、すべての形が重ならず等しい大きさに配置され、さらにモチーフ同士が関連しあって一見オールオーバーな画面には何本もの方向線が走り、いくつもの構図が見えてきます。児童画の根元性が、高い技巧に縁どられたとでも言いましょうか。じつに“名人”の趣です」。

「『ねがい星』もいいですよ。扉ページに続く最初のページの1コマ目。蓋をするように、『ドシン』『ドンガラガッチャ』『ガタガタ』『ドサドサ』というオノマトペが入ってきますが、このカタカナの連なり、形自体が持つリズムや配置の妙が画面全体を揺さぶりだします。右側から画面の端へスッと抜ける文字。抜けた先の埃の漫符が吹き出しへとメタモルフォーゼしてゆくのと交叉するように、オノマトペが色を軸にして散乱するアイテムへと変容し、4コマ目の統合を見る鮮やかさ。『天地7寸5分』と上下の矢印がそれらを無限円環へと導いています」。

「マンガだ、絵だ、などといってはいますが、鑑賞する側は、その作品が発している匂いのようなものを嗅ぎ分け、見分けつつ垣根をとっぱらっているというのかな。同じところに区分される絵だとしても、脳の触わられ方って全然違う。観た瞬間は分からなかったとしても、ふと思い出したときに、それが脳の回路のどこを通ってやってくるかは全然違ったりする。描き手としては、ああ!ここをこうじゃなくて、こっちをこう、ここにくる感じの絵を描きたい!と日々考え、絵を描いているわけです」。
ペンが動き、揺れて止まって線がひかれる。マンガ家の手つきを垣間見せ、その心根まで想像させてくれる『ドラえもん』の原画は印刷されてもなお光を放っている。コマが抜かれ、マンガのフォーマットからも物語からも距離をとった『THE GENGA ART OF DORAEMONドラえもん拡大原画美術館』を眺めれば、そこに潜むいくつもの意味と絵の魅力が浮かび上がってくるだろう。

(c)藤子プロ・小学館