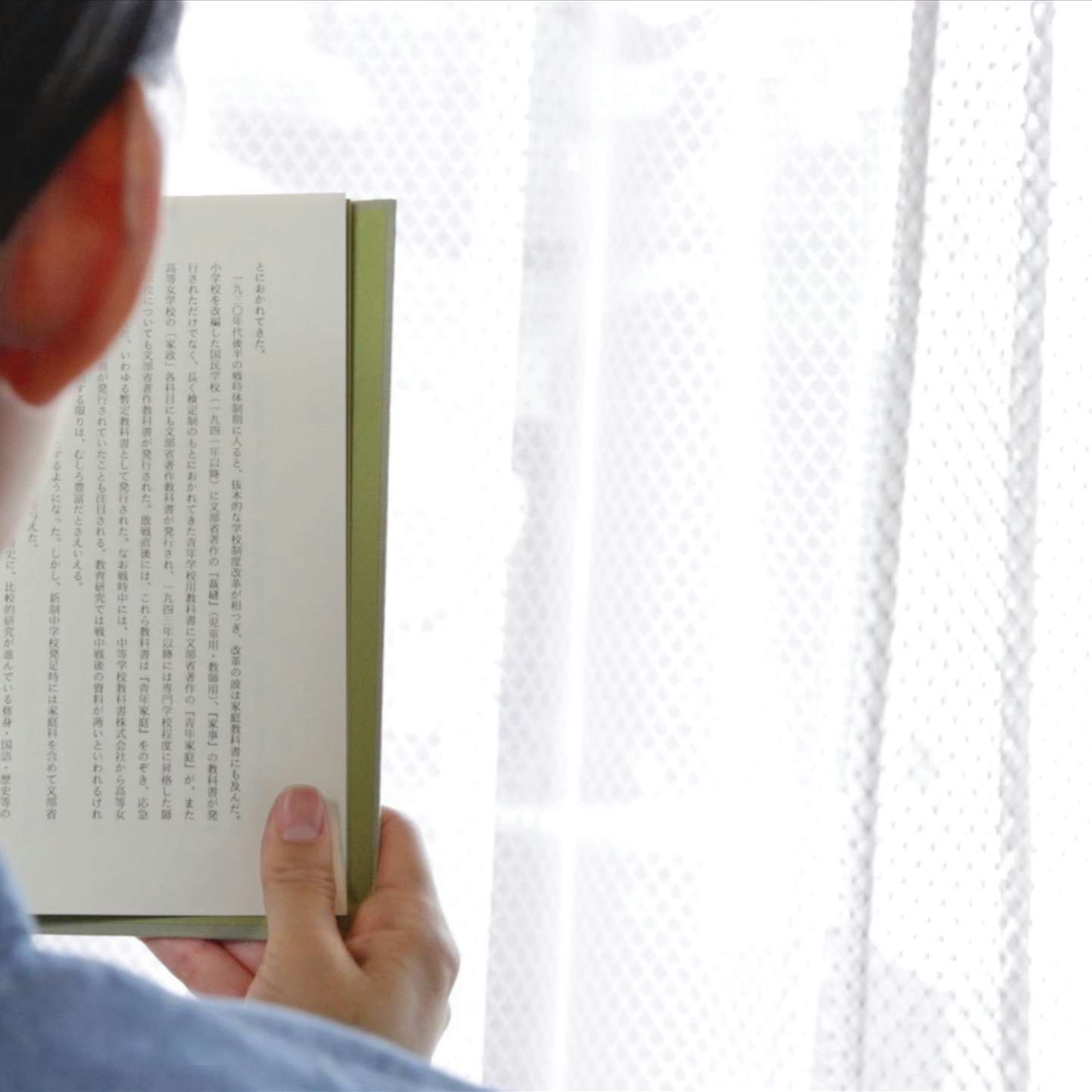語りきれない「家庭」の姿を展覧会で想像する。正路佐知子評「アカルイ カテイ」
時代の移り変わりとともに現れる様々な「家庭」のかたち。これを、美術を通して考える展覧会「アカルイ カテイ」が、広島市現代美術館で開催された。11組の作家たちが表現するそれぞれの「家庭」からは、どのような私的領域が見えてくるのか? 福岡市美術館学芸員・正路佐知子がレビューする。

明治大正生まれの作家から1980年代生まれの作家まで11人を取り上げる「アカルイカテイ」展は、「家庭」や「家族」といった言葉や概念が近代において構築されたものであるという基本に立ち返ったうえで、美術作品のなかに近代的な家庭像への懐疑あるいは解体の可能性を読み取り、あるいは新たな家庭の姿を見出そうという展覧会である。
桂ゆきの《積んだり》(1951)では、いまにも崩れそうな木造の家屋の上下に籐椅子、ペンやインク、木製人体模型などが絶妙なバランスで積み上げられている。この不可思議な作品名は、同年作の《こわしたり》(北九州市立美術館蔵、非出品作)という対作品があることで成立している。先行研究において指摘されているように(*1)、本作に見られる木の根は生家の庭に聳え立っていた椎の大木であることから、描かれているのが桂の生家であることがわかる。本作制作時、桂は実家を離れ一人で暮らしていた。《積んだり》において実家と思しき家を今にも崩れそうな姿で描き、《こわしたり》で画面を分断すると同時に家を解体することを厭わない態度に、封建的な「家」の抑圧に対する抵抗の意思と解放感をも読み込める。それは桂の個人史にのみ帰する話でもない。戦後、ようやく規定された家庭における「個人の尊厳と両性の本質的平等」(憲法24条)は言い換えれば、男女不平等と支配・服従関係を強いた家制度の解体でもあった。

(憲法と同じく)1947年にGHQによる新教育制度のもと新設された教科である家庭科に注目した川村麻純の映像作品《Family Living》(2019)は、誕生当時から現在までの家庭科教科書における「家庭」に関する記述を抜粋し朗読する映像と、GHQの一部局であったCIE(民間情報教育局)によって1950年に製作された教育映画『明るい家庭生活』によって構成される。
前者の映像では、女性が家庭生活に専念することこそが望ましいといった性別役割分業を推奨するような近代的な家庭像が続けて朗読される。憲法で規定されたはずの家庭における両性の平等はいったいどこへ消えたのか。唯一、最後に読まれる、父母そして姉と「ぼく」という家庭の構成員各人が家庭生活に関わり家事を行う日常の一コマに、ようやく現代的な家族のありようが語られたと安堵するも、それはじつは1947年の家庭科の教科書からの抜粋であるという事実。旧来のイデオロギーを手放せなかった戦後日本の教育は、家制度の時代とあまり変わらない家庭観をわたしたちに刷り込み、家庭の形成にも影響を与えてきた。女性が淡々と朗読するシーンに差し挟まれる無人の家事労働の現場に、誰がいる光景を思い浮かべるだろうか。
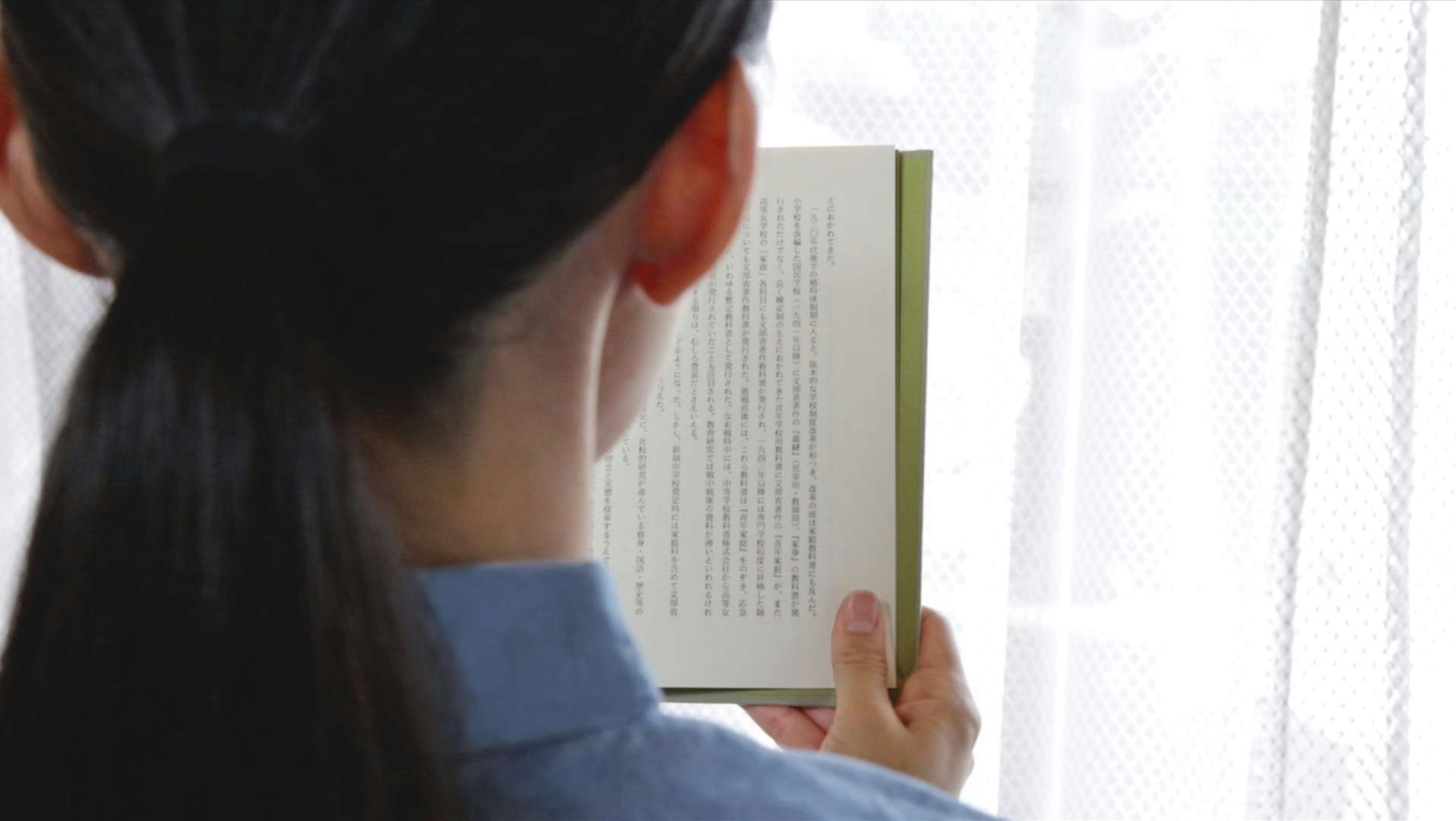
日本の近代的家庭観によって女性に押し付けられた「主婦」という役割に対して、出光真子の映像作品は、映像というメディアにおいて独自の手法に挑戦しながら、再生産され続ける保守的な家庭の息苦しさや、主婦の孤独といった現実をアイロニカルに描き出す。潮田登久子の「冷蔵庫」のシリーズ(1983-)は、近代的な家庭観のなかで、女の領域と見なされてきた台所に家庭の奥に鎮座する冷蔵庫に焦点を当てている。モノクロームで捉えられたその風景は、女の云々と言うよりも、その家の生活そのものをうつし出している。一枚岩ではない個々の家庭とその構成員たちの関係性が透けて見えるようだ。

「家庭」という大きなテーマで近現代美術を見るという新鮮な切り口によって、鑑賞者は現代社会が抱える問題と様々に接続する(し切り離すことができない)家庭生活に思いを馳せることになる。だからこそ、欲を言えば、普段なかなか表に出てこない私的領域である家庭の多様なあり方に出会いたかったとも思う。例えば封建的な(実)家から離れ、画家としての活動を続け美術界に大きな足跡を残した桂ゆきが「幸か不幸か奥様にもならず」(*2)生涯独身であったことに思い至れば、家庭はまた別の顔を見せるだろう。家事労働としての手芸、ひとり親や貧困、高齢化社会の問題、さらには出産や子供といったテーマに踏み込むことも、国際結婚や異文化結婚を経た家族や同性のパートナーシップについての言及も可能だったのではないか。あるいは男性と家の関係はどうすれば可視化されるのか。

しかしこれらの欲は、それらの問題に触れる作例がいくらか取り込まれていたところで、満たされるものでもないようにも思う。だからだろう本展では、その語りきれない家庭のありようを鑑賞者の実体験と想像力で補えるような作家選択と構成がなされていた。殊に、和田千秋の「障碍の美術」シリーズと息子・愛語による絵は、閉じがちな現代美術を社会に開いただけでなく、家庭が社会との結びつきなくして成立しないという当たり前の事実にも気づかせる。主婦たちへのインタビューを経て彼女たちからもらった生地を縫い合わせて、そこから物語を紡ぎ指人形劇というかたちでそれを披露する佐々瞬の《旗の行方》(2016)と、夫と妻と娘というステロタイプな関係にとどまらないあり方をうつす植本一子の写真《うれしい生活》シリーズ(2018)は、それぞれに近代的意味での「家庭」をときほぐした先の家庭について語っていた。



*1──関直子「桂ゆきのエニグマ」『平成26年度 東京都現代美術館年報 研究紀要 第17号』2015年、pp.85-91.
*2──桂ユキ子「自画像」『美術手帖』41号、1951年4月、p.47.
*3──本展覧会広報のメイン画像にも用いられていた植本の写真が、商店街のアーケード懸垂幕に使用しようとしたところ、中央の少女の姿が「公序良俗を害するおそれに抵触する可能性がある」として判断され、最終的に白抜きで掲出されたことを耳にした。市民からのクレームに対する過剰な反応(もちろんクレームの想定は必要だが、これは市民への不信による怯えからの検閲にほかならない)と、文脈や意図を聞き入れず個人的主観によって判断を下してしまう思考停止は、昨年からさらに増している実感がある。美術館側がどんなに説明しても理解が得られず不本意にも白抜きにせざるを得なかったというこの事例は、過剰な忖度が珍しく表面化したものに過ぎないかもしれない。