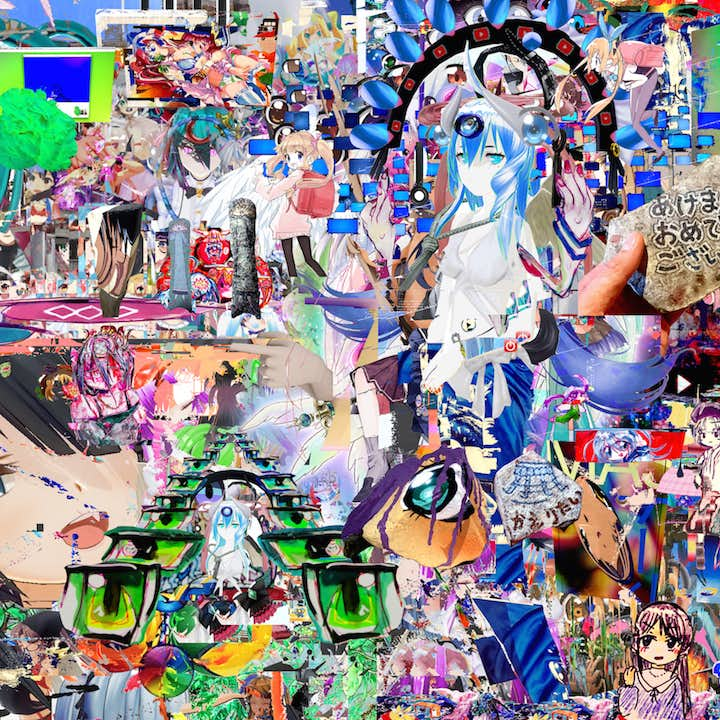現代の作家は「ジェンダー」に応答できているか? 美術家・黒瀬陽平インタビュー
シリーズ:ジェンダーフリーは可能か?(7)
美術手帖では、全11回のシリーズ「ジェンダーフリーは可能か?」として、日本の美術界でのジェンダーバランスのデータ、歴史を整理。そして、美術関係者のインタビューや論考を通して、これからあるべき「ジェンダーフリー(固定的な性別による役割分担にとらわれず、男女が平等に、自らの能力を生かして自由に行動・生活できること)」のための展望を示していく。第7回では、カオス*ラウンジの代表であり、「ゲンロン カオス*ラウンジ新芸術校」で5年にわたり講師を務め、アーティスト育成のための指導を行ってきた黒瀬陽平に話を聞いた。 ※編集部注:黒瀬陽平はカオス*ラウンジ 新芸術校の事業において、アシスタントスタッフへのハラスメント行為が発覚。被害者が詳細を告発する事態となった。こうした自体は深刻なものであるが、編集部では黒瀬が過去にジェンダーに関するインタビューを受けたという事実そのものは残す必要があると判断し、記事の削除は行わない(2020年8月4日)。

編集部注:黒瀬陽平はカオス*ラウンジ 新芸術校の事業において、アシスタントスタッフへのハラスメント行為が発覚。被害者が詳細を告発する事態となった。こうした自体は深刻なものであるが、編集部では黒瀬が過去にジェンダーに関するインタビューを受けたという事実そのものは残す必要があると判断し、本記事の削除は行わない(2020年8月4日)。
美術大学におけるジェンダーバランス
━━美術界におけるジェンダーバランスの問題が注目を集めています。黒瀬さんはジェンダーに関わる不平等について、何か感じていることはありますか?
ぼくは美術館などで働いているわけではないので、大きな組織の内部事情はよく知りませんが、ごく身近なところでは、美大・芸大におけるジェンダーギャップが思い当たります。美大・芸大は女性の学生が多い傾向にあると思いますが、教員の男女比を見ると、圧倒的に男性が多い。その点は明確な不平等ですし、実際に学生指導の局面でも問題が多いのではないかと思います。
しかし、美大・芸大に進学する前の美術予備校になると、講師の男女比率は美大・芸大ほど偏っていないのではないでしょうか。ぼくも都内の予備校で働いていましたが、現場で学生を指導する講師は女性も多く、男性中心の職場だと感じたことはほとんどありません。そう考えると、美術界も保守的で権威的なところに行けば行くほど、男性中心の社会になっているのかもしれません。実際、美術館の外で活動しているインディペンデントな現場では、女性のプレイヤーが多いと感じます。
━━「女子学生が多い」というお話でしたが、卒業後、実際に世の中で活躍するアーティストには男性が多いという印象です。これについて、批評家に男性が多いこと、つまり男性が言説をつくっていることが関係しているのではないか、という指摘もあります。
ある程度は関係している、とは思います。一口に「言説」と言っても複数あるわけですが、少なくも書籍や雑誌、新聞のようなメディアで筆をふるう美術の書き手には、男性が多い。たとえば、戦後の美術評論の御三家(針生一郎、東野芳明、中原佑介)のように、美術専門誌で書いている評論家はおじさんばかりだよね、という話はもちろんあるし、男性社会のすごく閉じたサロンでつくられた美術言説が、批判を受け付けないまま続いてしまっている面はあると思います。
ただ、そのことと美大の学内政治は、また違う問題ではないでしょうか。僕も内部にはいないので伝聞になるけれど、たとえば美大や芸大のなかで、誰が教授や学長になるかというのは、ほかの企業と同じく中年男性のコミュニティにおける「純粋」な政治であって、批評や言説とは切り離された世界だと認識しています。でなければ、なぜ美大や芸大では、作家や批評家としてはほとんど何の業績もないプレイヤーが要職に就くことが多いのか、という素朴な問いに答えられない。
━━教員と学生のギャップが生む問題では、多摩美術大学大学院の彫刻科の学生有志が大学に対してハラスメントに関する要望書を提出した件もありました。
美術を学びたい若い女性の学生に対して、男性社会で生きてきたおじさんの教員がどれだけ対応できるのか。学生は、内面にすごくデリケートな意識や問題を抱えている。そこにどれだけ踏み込んでケアできるかと言えば、現状はとても難しいと思います。意識的ではなく無意識のレベルでも、「男性だから/女性だから」という判断、思い込みはどうしても残ってしまいますし、それは知識や意識だけでは乗り越えることができない。男性教員ばかりだから理解してもらえなかったということは、美大出身のアーティストからもよく聞きます。

ラベリングを超えて、議論の質を求めること
━━黒瀬さんは美大や「ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校」で教える立場でもありますが、女性の学生に対してはどのように向き合っていますか?
とにかく学生の話を聞くことを意識しています。もっと正確に言うと、学生に喋らせることですね。多くの学生は、自分が考えていることをまだ上手く言葉にできません。言ってみれば言葉の解像度が低い。言葉の解像度を上げるために、まずは喋ってもらってそれをきちんと聞く。そして、言いたいであろうことと語っている言葉のミスマッチを指摘し、それを修正させる。さらにもう一度、喋らせる。この過程を繰り返していくと、本人の言葉の精度が上がってくる。そのチューニングのために、とても多くの時間を使います。
ぼくの経験上、美大ではこういう作業が圧倒的に足りていない。作品を見て、先生がなんとなくコメントを言って、終了、みたいな。つまり、お互いが他者であり、異なる言語で話しているという構えがないわけです。とくに新芸術校では、そうした部分にすごく気を遣いますよ。だって、一般から応募してきた受講生について、こちらは何も知らないわけだから。間違った対応で成長を止めたり、傷つけたりしてしまう可能性がある。
━━新芸術校の生徒の男女比はどのくらいですか?
ほぼ半分で、少し女性が多いくらい。ただ、先着順で採っただけです。新芸術校の生徒は1年目から本当にみんなの出自も年齢もバラバラで、ぼくの一回り上どころか、親や祖父母くらいの歳の方もいらっしゃいます。
━━ジェンダーだけでなく、世代差や立場の差が生むギャップもありそうですね。
そうですね。ただ美大に関しては、少なくとも女性教員が増えることで、「女性教員が少なくて女子学生の相談相手がいない」という現状は変えられる。ならばまずそこをクリアして、「女性教員はいるけれど話が通じない」という、次のレベルの議論ができるようにするべきだと思います。
━━美大の学生からは、ジェンダーに関する作品をつくろうとすると、先生から「それは茨の道だ」と諭されたという話も聞きます。つまり、「そのテーマでつくり続ける覚悟があるのか」と。
それはひどい。学生がそのときに提出してきたテーマをずっと続けるかなんてわからない。いま一生懸命考えていること、興味があることを作品にするのは、学校で成長していくうえで当然のことであって、まずは内容について話すべきです。それができないのは、教員が作品内容について議論する教育をサボっているに過ぎない。すべてをパターンで処理していて、「その学生」自身の問題を見ていないわけでしょう。これはジェンダー問題に限らず、美大でありがちな事態ですね。
━━これは美大に限らないですが、男性にとっては、女性がジェンダーや女性性について主張をすること自体、忌み嫌ってしまう部分があるのかなとも思ったのですが。
どうでしょう。いままでの話とその議論は別なんじゃないかと思いますが、そのレベルの偏見があるとしたら、論外ですね。ジェンダーを扱った作品も個別的な良し悪しがある。「ジェンダーを扱っているからダメ」と、「それゆえに良い」というのは、同じくらい雑なラベリングです。その次元を超えて、議論のレベルを下げないことが重要だと思います。

サブカルチャーの豊かなジェンダー表象
━━女性のなかにも、女性性が無批判に持ち上げられることに対する疑問の声というのはあります。
議論が成熟していないんだと思います。議論の蓄積やパターンが少ない。もちろん専門的な領域では研究の蓄積がありますが、それが現場レベルに降りてきていない。
ぼくも大学の授業でジェンダーに関する話をすることがあります。でも、ジェンダー論ではなくてコンテンツを紹介するんですよ。ぼくはジェンダー論の専門家ではなく批評家ですから、コンテンツを一緒に見ながら、考えましょうというスタイルを取っています。たとえば、女子美術大学で担当している授業では、「#MeToo」運動前後のサブカルチャーの話をしています。美大だから美術の話をしたいけど、現代美術史のなかでジェンダー問題を扱おうとすると、最低でも1960年代まで遡らなければならなかったり、たくさんの固有名や美術史的文脈を解説しなければならなかったりで、現代のアクチュアルな問題に接続するまでに時間がかかってしまうんですよね。
それに比べて少女漫画やBLコミック、ハリウッド映画や海外ドラマは、そのあたりの問題に敏感で、あらゆる批判を想定しながら「いま」の社会にアンサーを返している。だから限られたコマ数のなかで、いまのジェンダー問題を考えようとするなら、サブカルチャーを入り口にしてもいいんじゃないかと。
━━サブカルチャーとは、具体的にはどういった作品ですか?
先駆的なのは、ディズニー映画の『アナと雪の女王』。あれは2013年公開で「#MeToo」運動より前です。ディズニーは受け身なプリンセスばかり描いてきたけれど、『アナ雪』はそのことに対するディズニーの自己批評になっている。しかし面白いのは、『アナ雪』はむしろ極端な「逆張り」になっていて、あの世界に登場する男性はヘタレか詐欺師しかいない。つまり、男性がなんの役にも立たない世界を描いてしまっている。男性は役に立たず、女性だけで成り立つ世界のなかで、本当のマイノリティは誰なのか?という、複雑な問いに導かれる傑作です。
いっぽう「#MeToo」以降は、強い女性のあり方や理想を描く作品が増えます。それを一番突き詰めたのが『キャプテン・マーベル』(2019)。スーパーマンの女性版のような設定で、『アナ雪』よりもさらにシンプルな「逆張り」に見える。ただ、よく見るとあれはいわゆる「ガラスの天井」(*1)問題に対して新しいアンサーを返そうとしているようにも読解できる。キャプテン・マーベルと男性の師匠の関係をよく見ると、女性の社会進出を阻む「ガラスの天井」なんてじつはなかった、というメッセージを入れようとしたのかもしれません。
ほかにも、最近ではウェブで連載されているマンガ『青のフラッグ』(2017〜、集英社)、Netflixのドキュメンタリー『クィア・アイ』(2018〜)などは、いろいろと突っ込みたくなる問題点もありますが、批評的な視点を持った作品です。こうした作品についてちゃんと説明すると、学生も意見をぶつけてくれたり、自分もそうしたアイデンティティの問題を抱えていると相談してくれる。「あ、通じるな」と思いますよ。
━━美術の領域で、ジェンダーの問題につながる作品をつくっている、黒瀬さんが注目されているアーティストはいますか?
男性作家ですが、飴屋法水さんが思い当たります。飴屋さんは、つねに他者や不可能性について考えている作家ですから、自分が男性であること、自分が女性でないことについて考え続けていると感じます。飴屋さんには新芸術校にも講評に来てもらっていますが、その態度はしっかりと講評や生徒への対応にも現れていますね。
それから、サエボーグはモチーフとしてジェンダーを扱いながら、人間の欲望とは何か、という問題に迫ろうとしているように思います。ジェンダーを超えて共感できる哲学的な問題を提示しようとしている、尊敬できるアーティストです。

キャラクター表象の理解のために
━━カオス*ラウンジについてはどうでしょう? カオス周辺の作家が扱う美少女キャラクターの表象については、その男性主体的な視線について、とくに海外などから批判もあると思います。
去年9月、香港で行われた「セカイ系」と現代美術についてのフォーラムに参加しました。日本からは僕を含め3人と、ほかにイギリスや中国や韓国のアーティスト、研究者が登壇したのですが、その海外の方たちから、「日本の美少女キャラは、男性の欲望によって暴力的に女性のイメージを歪めている」という指摘が複数ありました。
たしかにその通りなのですが、そもそもそのようなキャラクターは、いわゆる「エロゲー」などのポルノコンテンツのなかから生まれている、という文脈があります。つまり、本来はごく一部の人の目に触れる小規模でアンダーグラウンドな文化だったものが、徐々に大衆的なサブカルチャーとして評価されるようになり、キャラクター造形などに大きな影響を与えている、というプロセスがある。本来的には日本国内でもアンダーグラウンドなものであり、その意味で、ある種のタブーと隣接していた表象なんです。
ところが、近年の「クールジャパン」が典型的なように、その背景を全部飛ばして、あたかも日本では美少女キャラがなんの抵抗もなく大衆に受け入れられているかのように国外にアピールすることは、大きな誤解を生んでしまいます。シンポジウムでの指摘は、そのような誤解によって生まれたねじれなのだと思います。
これは、村上隆さんが提起した問題の延長線上にある議論です。なぜ日本の一部のサブカルチャーは、こんないびつなキャラクター表象を生み出してきたのか。これに対して、村上さんは敗戦など歴史的、文化的な背景を考察して、ひとつの道筋をつけようとした。そのいびつさの起源を問うことが重要なのであって、クールジャパンのように「日本初の美少女キャラはこんなに世界中で愛されている」と宣伝することは、アートとなんの関係もありません。
━━性別にかかわらず、キャラクター的な表象を扱う作家は増えていますが、制作や発表にあたってどのような意識やプロセスが必要になると思いますか?
様々なアプローチが必要だとは思いますが、ひとつは、われわれはキャラクターというモチーフについて、どのような議論を蓄積してきたのか、その歴史を共有しようとする努力かなと思います。
例えば批評の世界では、大塚英志から東浩紀や伊藤剛につながるキャラクター論の蓄積があります。批評家が時代を超えて少しずつ、その土台をつくってきた。それくらい日本におけるキャラクターというのは、表現における重要なモチーフなのだと。そして、アーティストはその扱い方によって、現実との距離感や自分の考えを表明できる。だからキャラクターは、歴史のなかで時間をかけてつくられてきたひとつのモチーフである、という説明をすることは可能です。
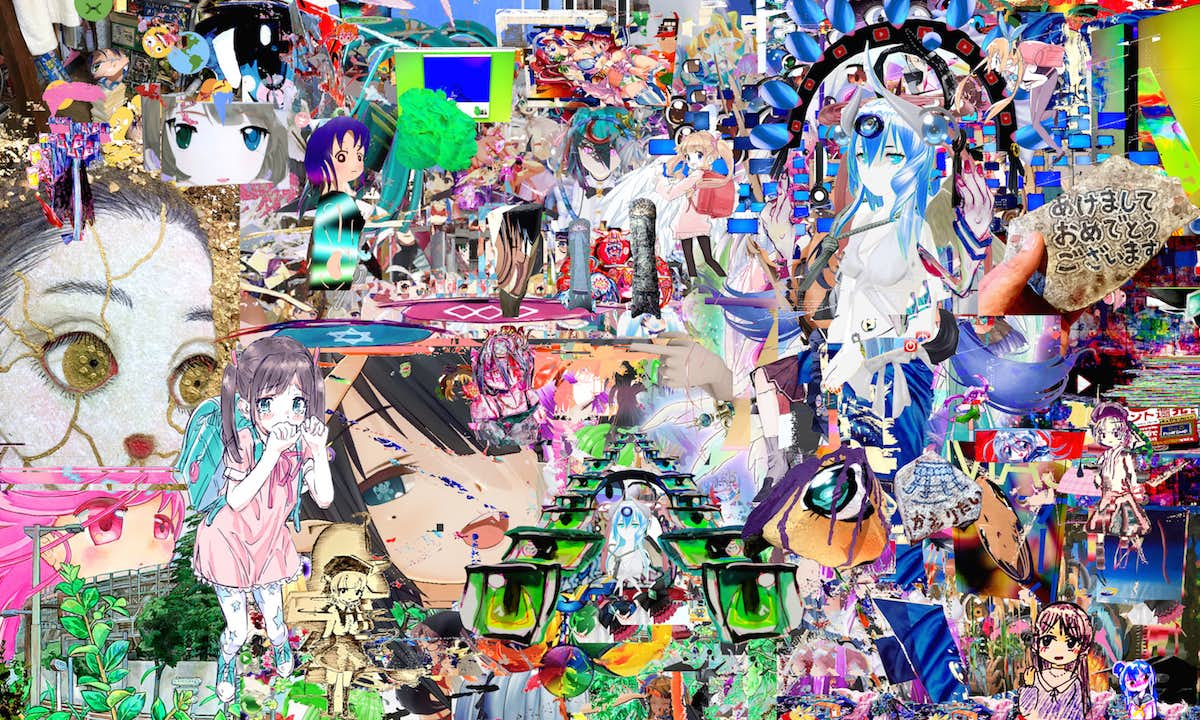
コレクティブと多様性
━━もう1点、カオス*ラウンジや新芸術校での経験をふまえてお聞きしたいのは、コレクティブや集団制作についてです。日本でもアート・コレクティブの歴史は脈々とありますが、多くは男性たちが組織する集団です。女性が参加する場合も、どうしても「紅一点」的な立場になりがちです。どうしてこのような構造になってしまうのか、何か考えていることはありますか?
それは美術界だけの問題ではないと思います。大きく言えば、義務教育の教室における男女の関係や、男性同士・女性同士の関係を反映している、ということに過ぎず、アート・コレクティブだから特殊な集まり方をしているわけではない。つまり、日本人がどんな環境で育ってきたのかという問題に関わっているのではないでしょうか。
ぼくにも息子がいますが、幼稚園や小学校のころから、誰が言ったわけでもないのに「男の子」「女の子」グループという風に、明確に同性の集団をつくる。そのなかで異性のコミュニティを遠くに眺め、同性同士で結束を固めるという習慣がついているのかなと。そうなれば、閉じられた男性のホモソーシャルなコミュニティにあえて入っていこうとする女性は自然と少なくなる。同じように、女性のコミュニティに男性が入ることも、ハードルは決して低くない。コレクティブのジェンダーバランスの問題はそのあたりに根があって、成人後の意識の問題よりもっと前に理由があると思います。
━━ホモソーシャルなコミュニティにおいては、優秀なリーダーであるために、どうしても強い男性性が求められてしまう、という問題も起こりがちだと思います。そのような問題も含めて、黒瀬さんが思う、あるべきコミュニティ像やリーダー像があれば聞かせてください。
重要なのはやはり多様性だと思います。強い男性性を求められるという問題は、男性同士のコミュニティや同じタイプの人間同士だからこそ起きやすくて、多様性によってある程度解消されるのではないでしょうか。ぜんぜん違う人生を送ってきた人が近くにいれば、お互いに変に期待し合うこともない。多様性がなくなり、自分への感情移入だけで結束する集団になると、リーダーはキツいということだと思います。
━━ただ、その多様性を担保することは、とても難しいことのようにも感じます。
アート・コレクティブに関して言えば、難しくはないと思いますよ。コレクティブは、作家がひとりで制作するのとぜんぜん違う。集団でつくる、組織なんです。組織としてやらなければいけないことを考えたとき、必要な人材は多様じゃないですか。
多様ではないコレクティブは、集団に見えてじつはひとりなんです。ひとりでやるのと同じようなことをしているから、同じタイプの人しか集まらない。だから、現代のコレクティブの問題点は、じつは「コレクティブじゃない」ということが本質でしょう。強い個が、自分のやりたいことを拡張するためにひとりで頑張っているコレクティブがとても多い。でも、それはひとりでやっていることの拡張でしかなく、表現として何も新しくはない。
ぼく自身は、将来的にはそうではないコレクティブを目指しています。これはジェンダーの問題から考えたというより、サステナビリティの視点から考えたんです。ある段階で、ワンマンのコレクティブの限界に直面し、このままでは長続きしないから、組織として人材を集め始めた。この人はつくり手ではないけど、仕事ができるからメンバーに加えないといけない、とか。そういうことを考え始めてから少しずつ変わってきたし、続けられる手応えを持てました。
理念と現実を同時に考える
━━最後に、アートにおいて、あるべきジェンダーフリーの状態とはどんなものだと考えていますか?
正直、いまのぼくには、そうした問題がすべて解決した社会を具体的に想像することができません。それは、ぼくの想像力の限界なのでぼくの責任なんですが、ひとつ思うのは、自分が生きている間に現実的にここまでは解決できるというヴィジョンと、自分が死んだあとであっても、理念的にはここまで解決できるだろう、というふたつのヴィジョンを持ったほうがいいのかな、と。
遠くの理念を語る人と、現実的な処方箋を考える人。この二者は、目線が違うだけで本来は対立していないのに、あたかも対立しているように衝突してしまうという状況が、現代における一番不幸な分断なのではないでしょうか。たとえば、「あいちトリエンナーレ2019」における津田大介さんのジェンダー平等の方針について、男女を同数にするという「形式を優先するのか」といった批判があります。しかし津田さんの提案は、現時点で何をやったら前に進めるのかというプラクティカルな処方箋であって、では、将来的にどうすればいいのかというのは次の議論です。実際、津田さんの提案は議論を先に進めているわけですし。
━━取材にあたって、じつは、男性にとってジェンダー問題を語ることには抵抗感もあるのでは?とも予測していました。そうした戸惑いは感じませんでしたか?
ジェンダーに関する専門的な議論であれば、ぼくも遠慮させていただいたと思います。専門家ではないですから。でも、専門的な勉強をしたという意味ではなくて、たとえば実際にぼくが運営している組織や職場には女性の作家や学生もたくさんいますし、コミュニケーションを取る時間もたくさんある。そういう実際の経験から考える、ということなら、誰しもが考え、語るべきだと思ったので、のこのこと出てきました。
*1──性別や人種などを理由に不当な状態を強いられ、組織内での昇進を阻む障壁のメタファー。