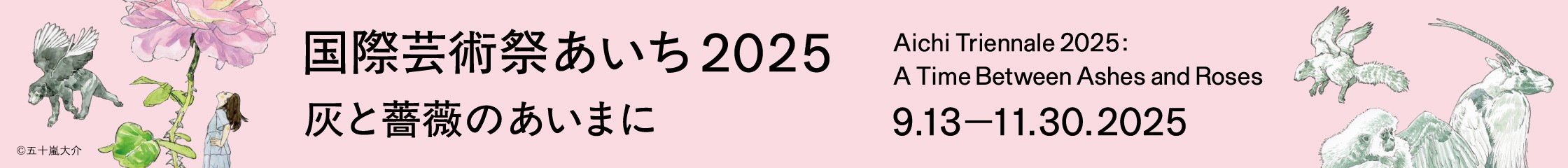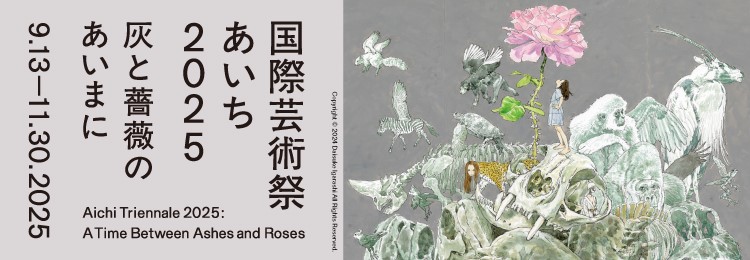このスナック「ジルバ」を始めて、もう40年になる。夜、スナックが開店し、気分が乗ってくるとステージ上での城田さんのカラクリ芝居は幕を開ける。披露してくれたのは、十八番の「番場の忠太郎」で、奥さんの軽快な前説で舞台の幕は上がる。自ら脚本を書き、照明・衣装・小道具などすべて手づくりという一人芝居は30分にも及んだ。時々、人形と人間の声色を間違えたり、上演するごとにセリフが違っていたりするのは、ご愛嬌だ。ほかにも「姥捨山」「九段の母」「三馬鹿踊り」など、そのレパートリーは幅広く、なかには人情劇もあり危うく涙しそうになるものもあった。
 舞台に立つ城田さん
舞台に立つ城田さん 城田さんは、自転車のハンドルに段ボールや廃材など、なるべくお金を掛けず身近な材料を工夫して、これまで50体以上のカラクリ人形をつくってきた。しかも、スナックという性質上、作品のほとんどがエッチなテーマだったり、性器をモチーフとしていたりする。「こういうことをするのは、余裕がないとできん。昔は食うていくのにようようじゃったけぇな。いま、夜の仕事じゃけぇ、昼間は時間が空くじゃろ」と壊したり、またつくったりしながら、時間があるときに1ヶ月ほどかけて、コツコツつくっているのだとか。
近年では、かかし祭りでの人形制作や熊を爆竹で撃退する「投げ玉」など、ちょとした街の発明家としても知られている。コロナ禍の際は、石油ストーブの蒸気を利用して、城田さん曰く、「コロナウイルスをやっつけることができる」という装置「コロイチ100%」を発明した。「投げ玉」は実際に熊に試したことはないし、「コロイチ100%」はもちろん効果なんて期待できないだろう。その効果も含めて信ぴょう性が大いに疑われても、皆から許容して貰えるところが、城田さんの愛すべきキャラクターの所以なのだろう。
アクセス面でも決して便利とは言えない場末のスナックだが、城田さんはいまもお客さんを楽しませるため、人形の制作や新作の芝居の練習を続けている。「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞」にも変わらず挑み続け、昨年は大会最高齢となる83歳で出場し、「熱戦!大相撲」という演目で20点満点を叩き出した。僕はそんな城田さんの挑戦し続ける姿勢に心打たれ、あるときは「探偵!ナイトスクープ」で依頼者として宣伝したり、2021年に京都市京セラ美術館で開催された平成年間の美術を振り返る企画展「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989–2019」の中で紹介したりと、様々なメディアを使って後押しを続けてきた。何度かバスツアーも開催し、たくさんの人にスナック「ジルバ」へ足を運んでもらえるよう企画したこともある。ある日のツアーでは、迎えのバスがジルバのトタン屋根を壊してしまい、大きな音を聞いて、ツアー参加者や芝居を終えたばかりの城田さんたちは慌てて外へ飛び出した。詰め寄る城田さんと必死で謝罪するバスの運転手の姿に静まり返るなか、センサーでカラクリ人形が動き出したのは良い思い出だ。僕が転居したあとは、地元のスパイスカレー店がコラボを持ちかけるなど、現在も応援の輪は広がっている。
これまでの話に象徴されるように、城田さんは、きっと多くの理解されない人たちから非難を浴び続けてきたことだろう。でも、どんなに馬鹿にされても、城田さんは決してやめなかった。そこには、いかなる批判をも打ち返すことができる、表現することの喜びがあるからだ。もう彼の耳には、どんな罵声も届かない。むしろ、あらゆる誹謗中傷が追い風になっているのかも知れない。たまたま情熱を傾けたものが、性的な表現だったに過ぎないのだから。いま、僕らに必要なのは、それらが卑猥な表現だからといって、決して目を背けないことだ。いかなることがあっても自分の信じた道を突き進む、これほど粋な高齢者を僕は知らない。今宵も自作の人形とともに、ステージの幕は上がる。
 城田さんの最新作はミックスジュースとかき氷がつくれる自転車
城田さんの最新作はミックスジュースとかき氷がつくれる自転車