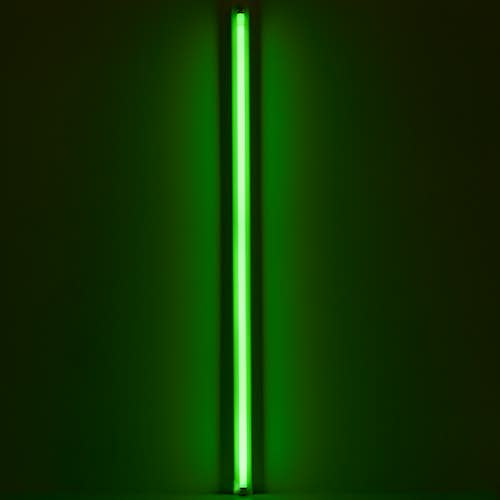フォンダシオン ルイ・ヴィトンの
コレクション展に見る、
世界と調和する“時代精神”
フランス・パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで、初公開作品を含むコレクション展「In Tune with the World(世界との調和)」が開催中だ。成功を納めた大型企画展「Being Modern: MoMA in Paris」に続くべく、ジャコメッティ、ゲルハルト・リヒター、村上隆、ピエール・ユイグ、アドリアン・ヴィジャール・ロハスら約30名の近現代美術作品を集め、テーマに沿って展観する本展。その見どころを現地からお届けする。

フォンダシオン ルイ・ヴィトンとは
白い帆をひろげて邁進する船のようなフランク・ゲーリーによる建築が初夏の青空に映える。LVMHグループによる財団が運営するパリの文化複合施設「フォンダシオン ルイ・ヴィトン」にて、財団の所蔵作品を新たに紹介する「In Tune with the World(世界との調和)」展が8月27日まで開催中だ。

フランスおよび世界に対して近現代美術を広める使命を担ったこの美術館の舵を取るのは、パリ市立近代美術館館長を経てフォンダシオン ルイ・ヴィトンが設立された2006年から芸術監督を務めるスザンヌ・パジェ。ラグジュアリー業界大手LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトンの資金で、20世紀以降の美術史をふまえながら、視覚的にも楽しく、また様々な考察を促す作品の多い独自のコレクションを形成してきた。
2014年の美術館オープン以降は、その所蔵作品を紹介するコレクション展と、外国の大型近現代美術館とのネットワークを活かした企画展などを実施している。ロシアの実業家シチューキンが収集したフランス近代絵画の傑作等を紹介した「近代美術のアイコン – シチューキン・

「世界との調和」展に世界のアーティストが集結
開催中の「世界との調和」展では、フランス近現代美術のスターをはじめ、90年代生まれの若手を含む国外人気現代作家の作品を厳選。それらを通じて、世界と人間の精神的な関わり方を探る展示構成が試みられている。
大きく2つに分けられた展示の前半は、村上隆に焦点を当てた構成だ。1993年の発表以来、アーティストを取り巻く環境と自身の精神性を反映し変化してきた「DOB君」が描かれた絵画群をはじめ、新たな表現を献身的に求めるやはり作家自身を写したパリ初公開の大型フレスコ画《タコが己の足を食う》(2017)、主題のキャラクター化に加えメディアミックスが顕著な《カイカイ&キキ》(2000)や《カニエベアー》(2009)などの彫刻やアニメーションも紹介されている。
日米のクリエイティブビジネスや東日本大震災以降の考察を更に深めつつ、世界を舞台に創作活動を続ける村上による仏教画や聖書の新約、伝説のアイコン化ともいえる表現には、“カワイイ”表層と物の怪が同居する。


後半は、「Man in the Living Universe」というテーマのもと、作品が3つのグループに分けて紹介されている。
まずは、蛍光灯を並べた作品で知られる米国出身のダン・フレイヴィンを中心に、世界を構成する光や水、鉱石や風といった自然界の物質に注目し、それらに対するアプローチや化学反応、生態系などを考察する作品群。フレイヴィンの《無題》(1963)は、多義の象徴にもみえるその光源と照らされる空間のなかで、工業製品である事実と裏腹に作品と対峙する者に崇高な時間さえももたらす。
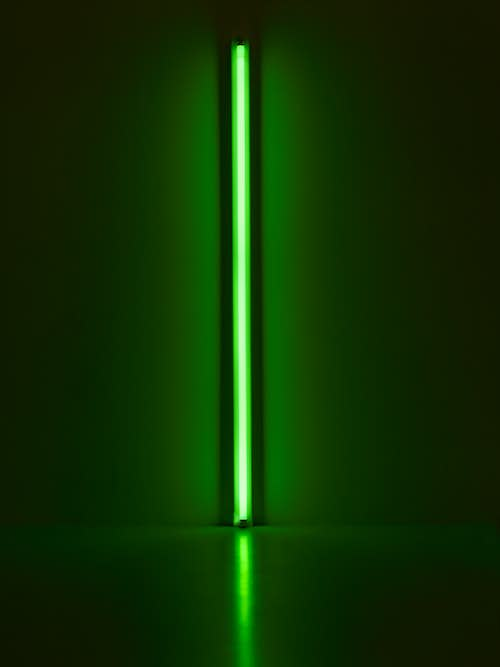
ドイツ現代絵画の巨匠からは、ゲルハルト・リヒターがとある風景を色と道具によるストロークで描いた《Lilak》(1982)と、ガラスの支持体に定着する顔料の動きをみせるために裏返して展示されるシリーズ《Flow》(2013)が並ぶ。感情を徹底的に抽象化した表層や、化学の原理が生み出した背景、それぞれの絵画体験に私たちを没入させる。

ミケランジェロやロダンといった彫刻家を参照した、アドリアン・ヴィジャール・ロハスとシプリアン・ガイヤールらの作品が暗喩するのは、人間の喪失の可能性だ。
ロハスはSFやバンド・デシネ、クラシック音楽などから着想を得ながら、夢の世界を具体化したような彫刻を制作する。2011年の第54回ヴェネチア・ビエンナーレでアルゼンチン代表に選ばれ、昨年はニューヨークのメトロポリタン美術館のルーフトップ展示にも37歳と史上最年少作家として抜擢された。《The Theater of Disappearance》(2017)では、ミケランジェロのダビデ像の膝上が喪失し、足下では2匹の猫が戯れている。「未来の考古学」と題して、最新の写真測定技術と3Dプリンター等を用いて再構成した本作。失われた部分が記憶で補完されると同時に、加えられた部分によって人間不在の架空のストーリーが物語られる。

最後の部屋では、人間の身体の変容が紹介されている。ジャコメッティは《ヴェネチアの女》(1956)で彫刻表現の肉付けなどを最小限までに削ぎ落とし、人間存在の難しさや脆さを訴えた。その不動性に対して、実在もしくは架空の人物を自ら演じるパフォーマンスで、現実とフィクションの関係を探求するドミニク・ゴンザレス=フォルステルの《M.2062(Fitzcarraldo)》(2014)では、身体はホログラムとなりその自我が誇張され非現実の舞台を徘徊する。いっぽう、東日本大震災後の福島という現実の世界を撮影したピエール・ユイグの《無題(ヒューマンマスク)》(2014)では、能の面をつけた猿がウェイトレスを演じる。ディストピアを暗喩した世界で、人間の精神性が動物や非実態の像に宿る姿がそこにはあった。
ハンス・ウルリッヒ・オブリストの司会で開催された村上隆によるアーティストトークでも指摘されたとおり、時代はAIの発展などでさらに高度化・複雑化し、人間存在やアートの可能性が問われている。本展はそのただなかで、深度を増す精神性が反映された現代の作品とともに、近代の作品の普遍性の強さも再認識できる展示だ。