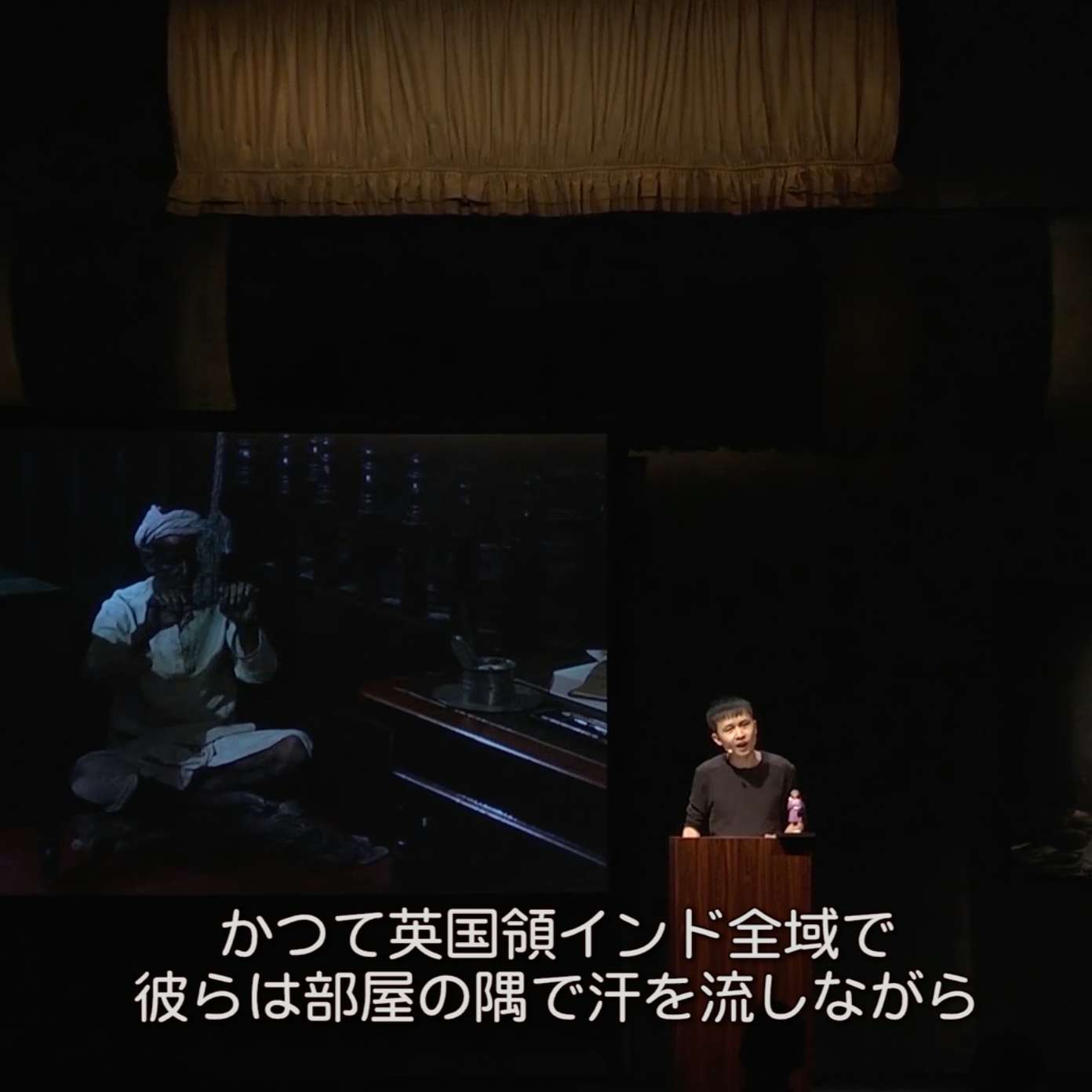地方から世界水準の芸術教育を。倉敷芸術科学大学・川上幸之介研究室インタビュー
現代美術の可能性を拡張するアーティストやスペース、プロジェクトを取り上げるシリーズ「美術の新たな目つきを探して」。第6回は、世界的に著名なアーティストやキュレーターとのコラボレーションを数多く実現させてきた、倉敷芸術大学の川上幸之介研究室に話を聞く。

岡山県にある倉敷芸術科学大学芸術学部の川上幸之介研究室は、「EEE(Education, Education and Education)」と題した現代アートプロジェクトを行っている。EEEでは、学生とともに、世界的に著名アーティストによるコラボレーション展や、 キュレーターや美術批評家、思想家 社会学者、哲学者などによる講演会、外部に向けた講演活動、ワークショップ、イベントなどを実施。加えて、東京大学AMSEA(*1)、東京藝術大学と共同プロジェクトを行うなど、多彩な活動を通じて次世代の芸術家を育成することを目指し、 教育によって知性と感性の融合を試みている。
2013 ジョン・バルデッサリ
2013 ライアン・ガンダー
2014 ジョシュア・オコン
2015 ミハイル・カリキス、ヘクトール・サモラ
2016 リクリット・ティラワーニャ、トーマス・ヒルシュホルン、サンティエゴ・シエラ
2017 ギー・ドゥボール
2018 ミヌーク・イム
2019 アントン・ヴィドクル
2019 ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニ
2019 ナイーム・モハイエメン
2019 ホー・ルイアン
2020 ハルーン・ファロッキ
2020 ゲリラ・ガールズ
(倉敷芸術科学大学・川上研究室の研究実績より)
先鋭的な授業内容で、全国の美術大学のなかでも異彩を放つ川上研究室。講師の川上幸之介が、その実践の礎となっている自身のバックグラウンドや問題意識について語ってくれた。

──川上先生は、イギリスで作家活動をスタートされたそうですね。現在に至るまで、どのような活動をされてきたのでしょうか。
高校卒業と同時に渡英し、ブラッドフォードで3年間過ごしたあと、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズでファインアートを専攻し、そのまま大学院まで行きました。在学中は、現在ブラックアート&デザインを専門とするソニア・ボイスが指導教官でした。彼女はアフロ・カリブ系イギリス人のアーティストなのですが、イギリスの黒人女性としては初めて、2021年のヴェネチア・ビエンナーレ イギリス代表に選ばれましたね。しかし在学中は、カルチュラル・スタディーズやポストコロニアリズムなどの話はせず、たわいもない内容ばかり話していました。いま考えるともったいなかったです。
私の過去の作品は、工場、リゾート地、構成主義建築など、資本主義や社会主義的といったイデオロギーが内在する建築物をコラージュで表現するというものでした。卒業制作を機にBearspace Gallleryに所属、その後Pippy Houldsworthへと移り、帰国直前まではひたすら作品を制作していました。当時のイギリスでは、1991年にダミアン・ハーストが展覧会を企画したことを皮切りに「Young British Artists(YBAs)」(*2)が盛り上がり、美大卒業後すぐにアーティストたちが自ら展覧会をつくるという流れがありました。そういったDIYの姿勢を見習って、私自身もキュレーションと制作どちらも行うようになりました。その後、家族の問題や自身が白内障を患うなど、様々な要因が重なって帰国し、2013年から現在まで倉敷芸術科学大学の教員、アーティスト、キュレーターとして活動しています。

──川上研究室では、2013年のジョン・バルデッサリを皮切りに、ライアン・ガンダーやジョシュア・オコン、ミハイル・カリキスら世界的なアーティストとコラボレーションしています。こうしたビッグプロジェクト実現の背景と狙いを教えてください。
最初のコラボレーションは、学生が美術史、とくにコンテンポラリー・アートを学ぶうえでもっとも重要な作家は誰かを考え、何人か候補を挙げながら、最終的に教育者でもありアートシーンへの影響力も大きいバルデッサリに決めました。美術史を重視する理由は、学生たちに「自分がいま歴史の延長線上のどこにいるのか」を再考したうえで創作の展開を考えてもらいたかったからです。
バルデッサリのプロジェクトでは、彼が学生たちに向けてギャラリーの壁に“I Will Not Make Any More Boring Art”(私はもう退屈なアートはつくりません)と描くことを遠隔で提案した《I Will Not Make Any More Boring Art》(1971)と、「アートフォーラム」誌に掲載されたソル・ルウィットのエッセイ『コンセプチュアル・アートに関する断章』(1967)をパロディ化した作品《John Baldessari sings Sol LeWitt》(1972)の2点の再制作に取り組みました。
《I Will Not Make Any More Boring Art》は、学生たちが、バルデッサリの指示通りにその言葉でギャラリーの壁を埋め尽くしたことを用いて、美大に残るアカデミックな伝統を批判した作品です。この芸術や芸術教育への異議申し立ては「芸術とはなにか」という問いへ繋がり、とりわけ教育の現場における教員と学生という非対称的な関係の考察へとつながりました。本プロジェクトでは、学生とともにそういった現代アートの手法を体感することで、芸術のみならず「教育とはなにか」という問いを検討できました。
その後のプロジェクトは、とくにラディカルな批評性を持った作品を手がけるアーティストたちに私が直接コンタクトを取って実現してきました。いずれも集客率といった経済的指標や国家権力からの検閲、アート関係者、またはアーティスト自身の自己検閲による展示への憂慮を取り除き、芸術活動に多様性を生むこと、そしてなによりアーティストやアーティストを志す学生に、そういった指標に合わせる必要がないことを示し、教育環境へと還元していくためでした。


──世界の変化に素早く応答していくために、川上先生は常日頃からどのようなリサーチや考察をされているのですか。
個人的に重要だと考えているキュレーターの展覧会は、国内外問わず、なるべく学生を連れて見に行くようにしています。やはり言葉で説明するには限界がありますし、リアルを体感したほうが理解も早い。コロナ前は、4年間で3~4回ほど、台北ビエンナーレや光州ビエンナーレ、ドクメンタ、ミュンスター・スカルプチャー・プロジェクトといった国際展への海外視察の機会を設けていました。
世界の変化に応答していくためには、まずは自らが置かれている状況を把握し、外部からの情報を取捨選択し、様々な課題に対して自分なりの解決策を導き出す力を養う必要があります。昨今「アート思考」が注目されているように、現代社会が求めるアートの持つ力、つまり自分でゴールを設定し、実現までのプロセスを考えて取り組んでいく力にヒントがあると思います。
具体的に授業では、現代アートを通して、格差やグローバリゼーション、植民地問題、紛争、戦争、移民、難民、ジェンダー、性的マイノリティといった日本国内にいると見えにくい問題を純粋な時事問題として受け止め、またアーティストがそれらの問題をどのようにアートに転化させているかの二つの面から学んできました。これは、アートそのものだけでなく、アートに関連する人文科学全般における人々の協力があってできています。ちょっと硬く聞こえたかもしれませんが、学生みんな和気あいあいと楽しみながら課題に取り組んでいますし、公開講座後の飲み会はとても盛り上がりますよ。

──哲学、思想、歴史への無理解を問題点に挙げ、ハンナ・アーレントなどを参照しながら講義を展開されているそうですね。アーレントに関しては、昨年ドイツ歴史博物館でオンライン回顧展が行われた関係で再注目の機運が高まっており、海外のシーンとのタイムラグを感じさせません。
芸術作品を理解するうえで、あるいはごく普遍的な問題を検討するうえで必要な思想を学生と学んでいます。学生にただ作品を見せて、これは難民問題について、これは戦争の加害問題について……と説明したところで、芸術家がなぜその問題を取り上げ、新しい問いや見方を提唱しているのか、作品の背景を自分たちの問題と重ねて考えることはなかなか難しいものです。
私の力や、学生間のディスカッションだけではどうしても限界があるなかで、アーレントのテキストは、戦争における「責任と判断」について思考の限界まで徹底的に考え抜かれた考察であり、それが正しいと一概には言えませんが、昨今の難民問題や、日韓・日中問題といった戦争における加害問題を考えたり、また芸術家のコンセプトをより理解するために一つの側面を提示してくれるものです。言語化して久しい今日のアートに言説は必要不可欠だからともいえるかもしれません。
──川上先生の教育実践は、公的領域と私的領域の問題が地続きになっていることへの認識を促すものですね。美術界のジェンダーアンバランスに言及するゲリラ・ガールズの個展を開くなど、そういったプロジェクトを学内に閉じず、一般公開されていることも多い印象ですが、地域の方々からはどのような反応がありましたか?
2020年に開催したゲリラ・ガールズの個展では、北は北海道、南は九州からたくさんの方がお越しくださいました。蓋を開けると、そのほとんどが大学の先生やアート関係者でしたが、倉敷にあるKAGというカフェ&ダイナーが会場だったので地元の人々も集まりやすく、地方でも世界のアートシーンを体感できることを伝えられたことが大きかったです。
また文部科学省のCOC事業(*3)として、3年間地域のプロジェクトにも取り組んできました。プロジェクトでは学生と協働し、外国人移住者との連携や、残留孤児・婦人の方々との交流、地域の高校の先生方を中心とした戦争遺跡の調査・研究といった平和活動を行いました。

──先行き不透明なコロナ禍は、教育機関にとっても大きな試練だと思いますが、現在どのような工夫をされていますか。今後の展望もあればお聞かせください。
これまで当たり前だと思っていた世界が崩れ、学生たちは新しいシステムのなかでどう生きていくか悩み、また様々なメディアの意見に揺れ、不安を抱いているのが現状だと思います。授業では、文化人類学者の松村圭一郎さんや農業史研究者の藤原辰志さんの言説など、コロナ禍を生きるうえで指針となるような内容を授業に取り入れてディスカッションを行っています。
昨年からコロナ禍で急速にオンライン化が進むなかで、私自身もいかにコンピューターを揃えて学生たちに完璧な授業を届けるかということばかりに頭がいってしまっていたのですが、ある日学生のひとりが、自身の家庭の事情や単位について話すなかで、泣きながら「先生が作品を褒めてくれたことが救いになった」と言ってくれました。いま学生にとって重要なのは、オンライン講義のクオリティよりも、温かい言葉や距離の近さなのだとハッとさせられました。
また教育の現場にいると「本当はこれがつくりたいけど、やめておこう」というような学生の葛藤をよく目にします。自由な表現の場であっても自己検閲し、その声に抗うのをやめてしまう。彼らは、内なる声にせよ外からの声にせよ、つねに社会というシステムのなかで上手く生きていくことを子供の頃から呼びかけられてきているのです。これは芸術教育だけの問題でなく、社会全体の問題かもしれません。大学における芸術教育がどうあるべきか、私にはわかりませんが、学生たちにはプロジェクトを通じて、アートが持つ視点のズラしや未知なるものに自分を開く感覚を知ってほしい。そしてそれを応用し、生きていくために考える力へ変転させてほしいと思います。

──今回のインタビューには、川上研究室に現在在籍中の小野勇人、本城優、森田玲音の3名と、卒業生である木原未来も参加。それぞれ講義で得た発見と感想を教えてくれた。
小野
僕の代は男性比率が高いということもあり、LGBTQの授業やゲリラ・ガールズの個展の際に、女性が抱えてきた問題を考えることは正直難しかった。別の授業では、ポストコロニアリズムに言及したアーティスト、ホー・ルイアンの作品を通じて、アジアやアフリカに赴いた植民地主義時代の欧米人が隠してきた労働の歴史を知りました。女性が性暴力や性差別を受けてきた負の歴史や、汗(労働)にまつわる歴史があまり語られてこなかったことに共通点を感じ、重要な課題として受け止めています。
本城
LGBTQの授業では、いかに日本の性や人権に対する考え方が疎かで、それゆえに多様性への許容範囲が狭いということを知りました。様々なアートに触れながら、もっとおおらかで風通しの良い社会を思い描くようになりました。
森田
川上先生の授業を通じて、世界的・公的問題が私的問題でもあることを自覚して、ふと発した言葉が差別の表現になっていないかどうかを気をつけるようになりました。アートを入口に、つねに差別は言葉によってつくり出されているということに気が気が付きました。
木原
川上先生は、私たち学生を「世界に所属している一人」として真摯に授業をしてくださいました。ありがとうございます。
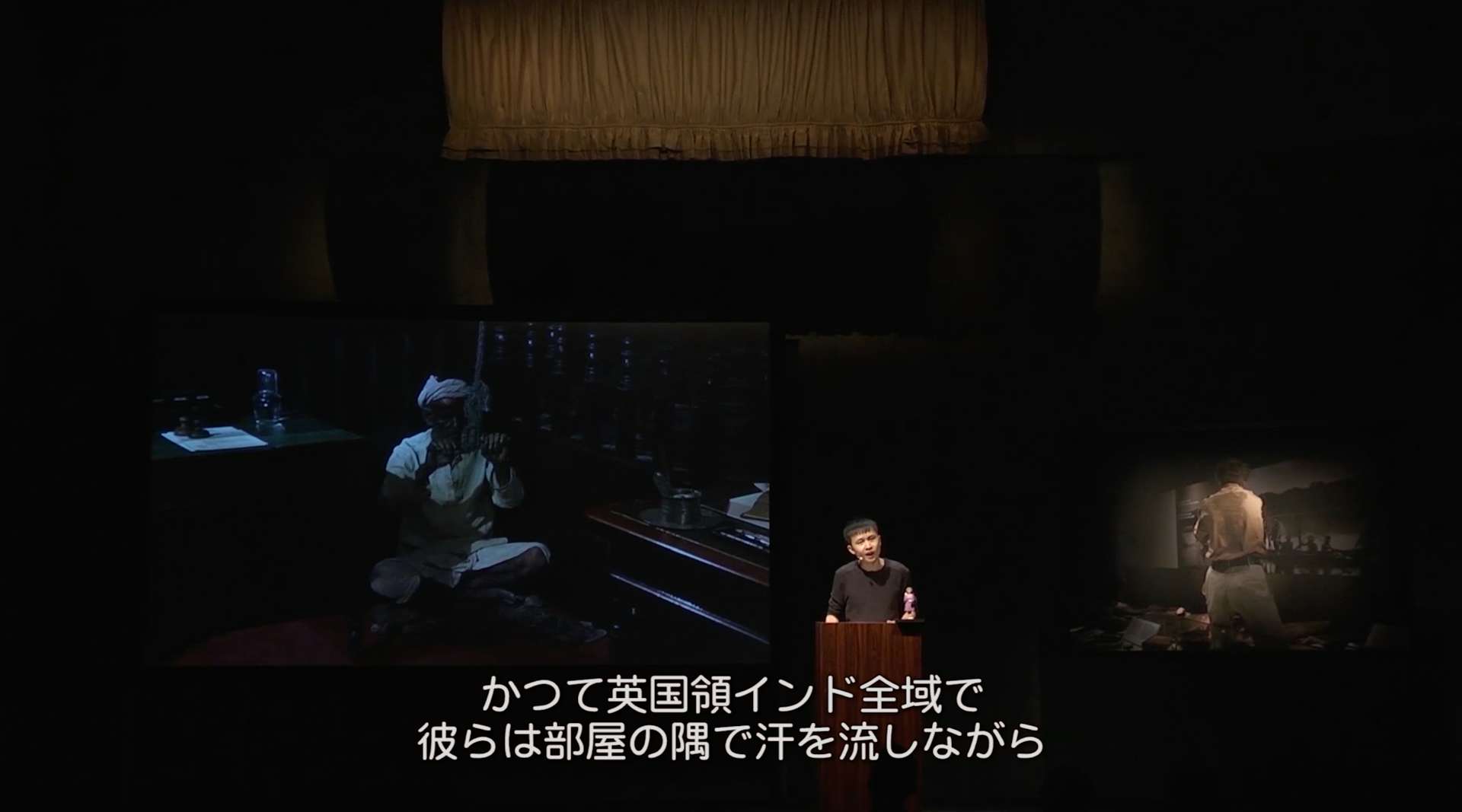
現在も企画展「PUNK! The Revolution of Everyday Life」を準備中の川上研究室。本展は、10組のアーティスト、アーティスト・コレクティブ、バンドに焦点を当ててパンク・ロックの系譜をたどるグループ展だという。
コロナショックの反省を得て、従来の大都市一極集中から教育・文化・経済活動の地方分散が進む今日。都市圏の文化事業が大きな打撃を受けるなか、自然豊かな倉敷では、コミュニケーションベースの芸術教育が光っていた。
*1──様々な差異を持った人々との共生を重視するアートマネージャーを育成するための東京大学を拠点とした教育プログラム。https://amseaut.blogspot.com/p/news.html
*2──90年代のイギリスの若手アーティストの一群や多様な展示活動そのものを指す。彼らの大半が80年代後半にゴールドスミス・カレッジを卒業したアーティストであるということ、そして自らキュレーションを行うDIY的精神を特徴とする。
*3──日本の文部科学省が、国内の大学を対象として「地域社会との連携強化による地域の課題解決」や「地域振興策の立案・実施を視野に入れた取り組み」をバックアップする施策のこと。