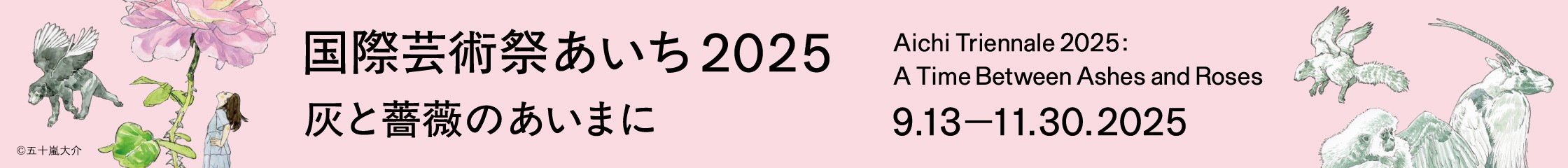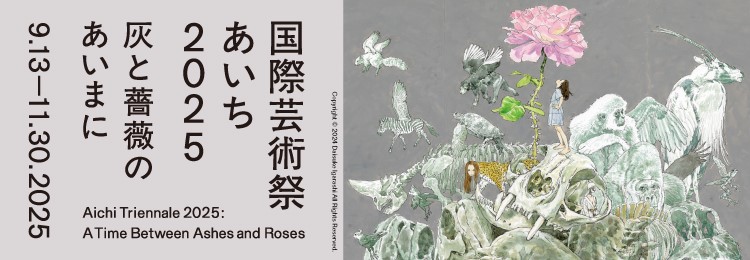江戸時代の「メディア王」の顔に迫る。特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が東京国立博物館で開催へ
江戸時代後期の出版業界に多大な影響を与えた蔦屋重三郎(1750〜97)。その業績を紹介する特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が、4月22日~6月15日に東京国立博物館で開催される。

江戸時代の傑出した出版業者・蔦重こと蔦屋重三郎(1750〜97)の業績を紹介する特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が東京国立博物館 平成館で開催される。会期は4月22日~6月15日。
蔦重は、浮世絵師・喜多川歌麿や東洲斎写楽を世に送り出し、江戸時代後期の出版業界に多大な影響を与えた人物。また、浮世絵や戯作、狂歌など、様々な文化的コンテンツを結びつけ、時代をリードする存在となった。蔦重の出版した作品は、当時の江戸の人々にとって新たな楽しみと刺激を提供し、出版業界における「メディア王」としての名を馳せた。

本展では、蔦重の多岐にわたる出版活動を、約250点の作品を通じて紹介する。会場は3章と附章で構成される。
蔦重の出版活動は、たんに本を発行するだけでなく、時代の流れを読み取り、優れた作者を見出し、彼らの才能を最大限に引き出すことにあった。第1章「吉原細見・洒落本・黄表紙の革新」では、彼が手がけた情報誌『吉原細見』や黄表紙、洒落本など、江戸文化の発展に寄与した作品が展示され、蔦重の出版活動がどれほど時代を先取りしていたかが明らかにされる。