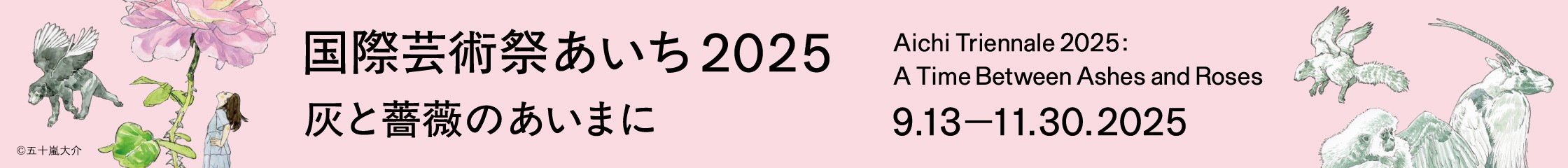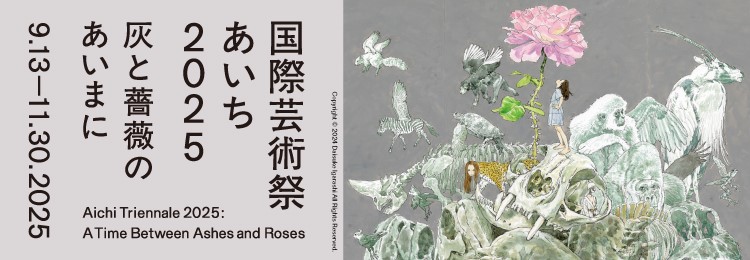櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:キング・オブ・セルフビルド
ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第82回は、35年以上の歳月をかけて独力で「理想宮」をつくり続ける饒波隆さんに迫る。

2018年1月に初めて訪問して以来、この場所を訪れたのは3度目だ。7年前に目にしたときに比べ、建物全体が緑で覆い尽くされている。よく見ると、植物の枝が侵食して道路にまで伸びている箇所もあり、通行の邪魔にならないようにと、ロープで引っ張っている部分もあった。少し離れたところから眺めてみると、まるで植物がゆっくりとうごめき、建物全体を覆い尽くしているかのようにも思えてくる。これは、沖縄県在住の饒波隆(よは・たかし)さんが35年以上の歳月をかけて独力でつくりあげている「理想宮」だ。
7年前は、岩山の中央から覗く窓が、その異質さを際立たせていたが、種々の植物で覆われた現在の光景は、とても個人の邸宅だとは思えない。そう、この場所は鉄筋コンクリート住宅に石を張り付けた、饒波さんの自邸なのだ。饒波さんはカルスト地形になっている近くの山から板状の石灰岩を拾ってきては、それらを積み上げ、石と石の隙間をモルタルでくっ付ける作業を、たったひとりで35年以上も続けている。